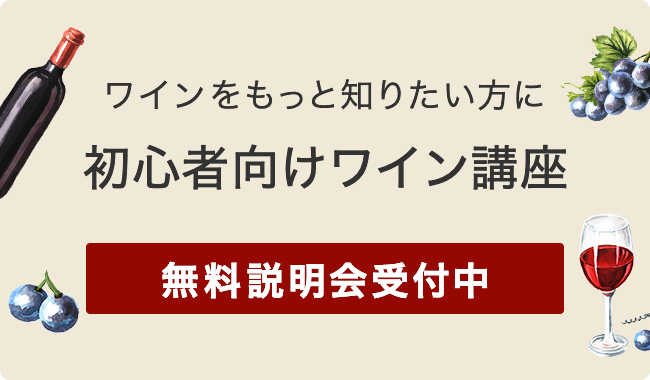スティーヴン・スパリュア。2021年に79歳で生涯の幕を閉じた、イギリス出身のワイン業界人。この男は、揺るぎない情熱と類い希な先見性で、1976年のある「事件」を通じて、ワイン界を大きく揺さぶった。「パリスの審判」と呼ばれたこの衝撃は、そのあと半世紀を過ぎて今なお続く、世界的な業界の発展と躍進に先鞭をつけた。ワイン商、教育者、批評家、文筆家、審査員、コンサルタント、イベントオーガナイザー、ワイン生産者といったいくつもの顔をもち、どのフィールドでも稲妻のような才能を見せてはばからなかった。上流階級の出身でありながら、気さくかつ温厚な人柄で多くの人々を魅了し、誰に対しても惜しみなくワインの見識を共有した。ワインに向き合う際は、伝統に敬意を払いつつも、徹底的にラディカルかつリベラルだった。泉のように湧き出た、ワインに対する飽くなき探求心は、伝統的な価値観に縛られていたワイン業界に新風を吹き込み、世界中のワイン愛好家やプロフェッショナルたちに、興奮と感動を与え続けた。英国紳士かくあるべしという、エレガントな所作と礼節の持ち主でありながらも、常に謙虚で物腰柔らかく、控えめな人だった。
本記事では、このスティーヴン・スパリュアという希代の人物について、多岐にわたるその活動と挑戦を追いながら、生涯と功績を振り返る。
【目次】
1. 裕福な生まれ育ち、ワインとの出会い
● 銀のさじを口にくわえて
● 育まれたふたつの愛情: ファイン・アートとワイン
2. ワイン業界入り、大金の贈与、現地修行、結婚
● 名門大学からワイン商の丁稚奉公へ
● 父から大金を受け取る
● ワイン産地めぐりと恩師との出会い
● 愛妻ベラとの結婚、プロヴァンスの予言
3. パリへの挑戦 – カーヴ・ド・ラ・マドレーヌとアカデミー・デュ・ヴァン
● 古びた酒屋を買い取り繁盛店に
● フランス初のワインスクール、「アカデミー・デュ・ヴァン」
4. 世界を驚愕させた「パリスの審判」 – こぼれ話
5. 逆風にさらされつつ、多方面で活躍した1980年代
6. ロンドンに戻る ~ 『デカンター』との日々と叢書の創設
7. ベルリン・テイスティングと世界凱旋の旅
8. ブライド・ヴァレー・ヴィンヤード – 英国産スパークリングワインへの挑戦
9. スティーヴン・スパリュアが愛したボルドーワインたち
10. スティーヴン・スパリュアを偲ぶ声
11. 結び:スティーヴン・スパリュアの人生を貫いた3つのS
1. 裕福な生まれ育ち、ワインとの出会い
銀のさじを口にくわえて
スティーヴン・スパリュアは、1941年10月5日、イギリスの都市ケンブリッジで産声をあげた。ランカシャー州で商業的な成功を収めた、裕福な一族の生まれだった。父方の祖父の兄弟は、1896年にランカシャー・スチーム・モーター・カンパニーを設立し、これが後に、ローバー、ジャガーなど多数のブランドを傘下に置く自動車会社、ブリティッシュ・レイランドへと発展した。祖父自身も、砂利と砂の事業で財を築いている。スパリュアの姓は、今から約400年前、1628年まで遡れるという大変由緒ある家筋だ。母方も同様に、豊かで長く続く一族だった。産業革命の時代、有名な織機の開発者と業務提携して富を手にし、ダービシャー州に病院や学校、公園を建設しては、自治体に寄付していたそうだ。「われらがヒーローは、銀のさじを口にくわえて生まれてきた」と、長年の友人であったイギリスのワイン業界人サイモン・ロフタスは、著書の中でスティーヴン・スパリュアをこう紹介している。
ロフタスの言葉どおり、スティーヴンは(本記事では以降、親愛の情を込めてスパリュア氏をファースト・ネームで呼ぶようにする)、兄のニッキーとともに、20世紀半ばのイギリス上流階級に見られる、典型的な環境で育った。祖父は、狩猟、射撃、釣りを好む地方の名士・大地主、かつ母方の叔父がスコットランドに広大な土地を所有していて、そこが狩猟や魚釣りにうってつけだったから、一家はそうした「田舎暮らし」の遊びを楽しんでいた。スティーヴンは狩りや釣りを、生涯の趣味にしようとはしなかったが、やがてブドウ畑のある界隈へと踏み込んでいったのは、幼少時から自然に触れる機会が多かったからかもしれない。
育まれたふたつの愛情: ファイン・アートとワイン
高貴な生まれのスティーヴンだったが、その両親は型にはまった価値観を、子供たちに押し付けようとはしなかった。父ジョンは戦前、出版業界で働いており、母パメラも、イギリスの代表的なタブロイド紙である『デイリー・ミラー』で、食とファッションの記者をしていた。ふたりは息子たちが自由な精神と探求心を育むのを重んじ、スティーヴンが幼い頃からファイン・アート、ハイ・カルチャーに触れる機会を与えたから、終生「アート漬け」の日々を送るようになった。スティーヴンといえばとにかくワイン、ワイン、ワインと語られがちだが、美術品・骨董品の蒐集家でもあり、「生涯、ワインよりもアートに費やした金額の方がずっと多い」と、本人も晩年に振り返っている。終の棲家となった、イギリス・ドーセット州の家も、絵画やオブジェで埋め尽くされていた。
スティーヴンが、ワインと出会ったのは、初めて長ズボンをはいたという13歳の冬だった。ダービシャーにあった一族の家での、クリスマス・イヴの夕食時。祖父が、「そろそろおまえもポートを飲んでよい歳だ」と声をかけると、ワイングラスとデカンターがスティーヴンのところに回ってきた。銘柄は、コックバーンのヴィンテージ・ポート、1908年。スティーヴン曰く、「とてつもなく素晴らしい体験で、その印象は生涯続いた。それが私にとって、『聖パウロの回心』であり、その後のワイン人生の種が、しっかりと植え付けられた瞬間だった」
2. ワイン業界入り、大金の贈与、現地修行、結婚
名門大学からワイン商の丁稚奉公へ
少年スティーヴンは、その後イギリス最高峰の名門私立校、ラグビー・スクールでの寮生活を経て、これまた超名門の、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(ロンドン大学の分校のひとつ)に進学した。ラグビー校の頃からワインについての本を読みあさり、大学では当然のようにワイン・サークルに加入、卒業後はワインの仕事に就くと決めていたという。父親はその進路を聞いて「どうかしている」と反対したそうだが、スティーヴンは意志を曲げなかった。大学卒業直後は腰掛け的に、百科事典を出版・販売する会社へと一旦就職するが、レストランで隣の席に偶然座っていた、ワイン商に勤める青年の紹介で、「ワインのプロ」への道が開ける。店は、ロンドンのジャーミン・ストリートにあるクリストファーズ。かくして、イギリス最古とされる老舗のワイン商で、スティーヴンの丁稚奉公生活が始まった。1964年2月、22歳のときである。

ラグビー・スクールの寮舎と校庭。スポーツのラグビー発祥の地とされる学校
父から大金を受け取る
クリストファーズでの修行をはじめて間もない1964年の春、スティーヴンは一夜にして大金持ちになる。家の事業を売却した父ジョンから、25万ポンド(今日の貨幣価値に換算すれば500万ポンド=約9億円)という、莫大な金額の贈与を受けたのだ。当時、ワイン商での賃金が月40ポンド、加えて親からの仕送り月60ポンドでやりくりしていたスティーヴンにとって、25万ポンドは想像を絶する大金だった。
「父は、この大金によって、私が完全に独立するよう望んでいた」と、スティーヴンは語っている。だが、父ジョンの期待とは裏腹に、この突然降りてきた財産は、若きスティーヴンを困惑させた。「完全に人生のバランスを崩してしまった」と、後年回想録の中で振り返っている。あぶく銭を手にした世間知らずの若者を標的にする、「悪い大人たち」に言われるがまま、ナイトクラブの経営や映画制作に出資したせいで、3年後には持ち金が半分まで目減りしてしまった。その後も、パリで始めた事業(カーヴ・ド・ラ・マドレーヌ、アカデミー・デュ・ヴァンなど)の外見的な成功にかかわらず、スティーヴンの両手からは金がこぼれ落ち続ける。大金の贈与を受けてから四半世紀がたった1980年代末には、「50歳を目前にして、ゼロから再出発する羽目になった」というから、残念な話である。スティーヴンは、才気煥発なアイデアマンで、地頭も大変よく、その華麗なルックスを含めて人を惹きつける天性の魅力の持ち主だったが、「金儲け」を成しえるために必要な、貪欲さやガッツは持たない人だった。お人好しで、彼を利用しようと集まってくる悪辣な者どもに、あらがう術ももたなかった。本人自身、「ビジネスには疎かった」と認めていたし、回想録に登場する次の告白、「決断するのが苦手で、選択肢を与えられるとほとんどいつも、間違ったほうを選んでしまう」は、スティーヴンの生涯の気の毒な「B面」について、吐露した言葉だと思われる。
ワイン産地めぐりと恩師との出会い
大金が転がり込んできてからも、クリストファーズでの見習い勤務は続けていた。有り難かったのは、旅費・滞在費は自腹だったものの、ブルゴーニュ、シャンパーニュ地方でそれぞれ収穫時期の研修労働に、店から派遣してもらえたという役得だ。その後も、スティーヴンのワイン産地巡りは続いた。8ヶ月間にわたって、フランスのボルドー、ローヌ、アルザス各地方、さらにスペイン、ポルトガル、ドイツ、イタリアと、名だたるワイン産地を巡り、時には研修生として働きながら各地のワインや文化に触れた。現場に足を運び、スティーヴンのワインに対する知識と情熱は、さらに深まっていった。
1965年が終わるころ、スティーヴンは老舗のクリストファーズから、マリー&バンバリーという新しくできた店に勤め先を変える。しなしながら、マリー&バンバリーの商売はほどなく行き詰まり、先がないと見たスティーヴンは、1967年に店を辞めた(その1年後に、この店は倒産している)。マリー&バンバリー時代のスティーヴンについては、生涯の師と仰ぐ「古酒の神様」、故マイケル・ブロードベント(1927-2020)に初めて会ったのが、最重大イベントになる。当時のブロードベントは、イギリス屈指の名門オークションハウスであるクリスティーズに勤め、ワインの取扱を再開(1966年)させたばかりだった。スティーヴンは、ブロードベントからいかにワインを味わうかについて、手ほどきを受ける。回想録の中でスティーヴンは、「マイケルの指導と友情、そしてその著書がなければ、私がパリに開いたワインスクール、アカデミー・デュ・ヴァンは存在しなかっただろう」と述べているほど、その影響は大きかった。スティーヴンの試飲能力は、飛躍的に高まった。ブルゴーニュの超名門生産者、メゾン・ルロワの当主であったアンリ・ルロワ(現当主ラルー・ビーズ・ルロワの父)がこの頃、一緒にテイスティングをしていたスティーヴンを差して、「この若者は、味わい方を知っている」と述べたというのだから、まだ20代の若者にはたいそう名誉な言葉であったろう。
愛妻ベラとの結婚、プロヴァンスの予言
生涯をともに歩んだ、愛妻ベラ・ローソンと出会ったのは、クリストファーズで働きはじめた1964年であった。ベラは1946年生まれだから、スティーヴンより5歳年下で、アイススケートリンクで初顔合わせしたときは、17歳だった。交際は順調に深まり(ふたりは一緒に、ヨーロッパのワイン産地を巡った)、3年後の1967年秋には婚約、翌年にプロヴァンスで結婚式をあげた。プロヴァンスには土地と家を買い、2年半ほどこの魅惑的な田園地帯で、新婚生活を楽しんだ。その後、パリに移ってからのふたりは、一男(クリストファー)、一女(ケイト)に恵まれている。
ベラについて知っておいてほしいのは、世界中で(この記事の中でも)使用されている、「パリスの審判」(後述)関連のモノクロ写真は、すべてベラが撮ったという事実である。後日、このイベントの記事を米国『タイム』誌に発表した記者、ジョージ・テイバーが撮影したのではない。ベラはパリ時代、名のある写真家のもとでアシスタントとして働いており、いわばフォトグラファーの卵だったのだ。「パリスの審判」が、今も語り継がれる伝説的イベントになったのには、ベラによる見事な写真の数々も大きく貢献している。
スティーヴンのプロヴァンス時代には、印象的な逸話がひとつある。地中海に面したリゾートの町、サントロペの波止場のカフェにいたスティーヴンは、通りすがりの占い師の女性に、気まぐれで手相を見てもらった。予言の言葉はふたつで、「3年以内の転職する」と、「永続的な名声の可能性」だった。当時無職だったスティーヴンにとって、ひとつめは起こりそうになく、ふたつめは荒唐無稽に思われたという。しかしながら、この予言はふたつとも、見事に的中した。
3. パリへの挑戦 – カーヴ・ド・ラ・マドレーヌとアカデミー・デュ・ヴァン
古びた酒屋を買い取り繁盛店に
1970年の夏が終わると、スティーヴンとベラはプロヴァンスを離れ、パリへと拠点を移す。セーヌ川にかかる、コンコルド橋近くに停泊する船を住処とした。「何もかもが楽しくて、何もかもがうまくいかないように思われた、パリでの魔法のような10年」と、スティーヴンが回想録の中で述べる日々が、ここから始まっていく。ワインショップとワインスクールの成功によって、多方面に向かう扉が開いていったのだ。パリの住まいに加えて、ブルゴーニュにも家を買い、南ローヌのヴァケラスにある優れたブドウ畑の権利を49%保有し、レストランを何軒も経営した。しかし、その次の10年が終わるまでには、すべてを失う羽目になっている。
ともあれ、1971年のはじめ、スティーヴンは、弁護氏の友人とレストランへ向かう道すがら、古ぼけた小さなワインショップの前を通りかかった。パリの中心8区、マドレーヌ寺院前の広場で、周辺には高級食材店が軒を連ねる立地である。その名は、わかりやすく「カーヴ・ド・ラ・マドレーヌ」と名乗る。「この店を買おう」とひらめいたスティーヴンが中に入ると、相対したおかみが、2年前から店を売りに出していて、値段は30万フラン(2.5万ポンド)だと告げた。しかしながら、マダム・フジェールという名のおかみは、目の前にいる異邦人の若者が、はたしてちゃんと店を経営していけるのか、疑念を抱いた。そこでスティーヴンは、「半年間、無償で働くので、その結果を見て判断してください」と、提案してみせた。
1971年4月にスティーヴンは、『ヘラルド・トリビューン紙』に「英語を話すワイン商がいます」という広告を出し、それまで安価なワインの量り売りが中心だった場所を、高級ワインの専門店に様変わりさせた。カーヴ・ド・ラ・マドレーヌは、英語を話すビジネスマンが多く働く地域に位置していたから、イギリス人が切り盛りするようになって賑わいを見せた。かくしてスティーヴンはマダムの出した試験をパスし、正式に店の経営権を手に入れる。新進のワイン商、スティーヴンは大胆だった。偉大な生産者の瓶詰めワインを扱うにとどまらず、小売店の側から生産者に提案をして、デゴルジュマン(澱抜き)の際に一切糖分添加をしないシャンパーニュや、シャプタリザシオン(補糖)をしないボージョレを「開発」して販売をしており、これらは時代を40年は先取りした感のある仕事だ。品揃えも幅広く、1970年代の半ばには、カーヴ・ド・ラ・マドレーヌはパリで最良のワインショップのひとつになっていた。

1981年、カーヴ・ド・ラ・マドレーヌの経営開始10周年を記念しての一枚。超一流生産者のボトルや木箱に囲まれて
フランス初のワインスクール、「アカデミー・デュ・ヴァン」
やがてスティーヴンは、カーヴの常連客たちから、ワインについてもっと知りたいという要望を受けるようになる。まずは、ショップの店内で小規模なワイン講座を始めた。これが好評を博し、やがて店の隣のビルに空きが出ると、本格的なワインスクール「アカデミー・デュ・ヴァン」を設立した。消費者にワインを教えるというコンセプトの学校は、フランスで初めてだった(「ワイン学校」を意味するその校名が、難なく商標登録ができたのだから、あにはからんやだ)。1972年8月の開校当初は、カーヴの常連客であった英語話者を対象に、すべての授業を英語で行っていたが、次第にフランス人のうちでも話題となり、フランス語の授業も開講するようになった。1973年の初めには、アメリカ人女性のパトリシア・ギャラガーが雇用され、スクールの運営を任された。ギャラガーはそれから3年後、ともに「パリスの審判」を仕切る、スティーヴンの片腕にして相棒となっていく。
アカデミー・デュ・ヴァンでは、創造的かつ革新的な比較テイスティングが、あれこれと開催された。馬蹄形をした試飲テーブルが、その象徴だった。シャトー・ディケムの名物当主、アレクサンドル・リュル・サリュース侯爵がフォワグラを持参し、そこに8つの一級シャトーが加わっての豪華なボルドー・テイスティング。ブルゴーニュ名門ドメーヌ、コント・アルマンの垂直試飲。1982年産ボルドーの樽抜きワインの水平試飲、などなど。ワイン生産者だけでなく、各国の大使館からも協力が受けられたから、1970年代後半という時代に、優れたオーストラリアワインや、チリワインを紹介するテイスティングも催していた。スティーヴン自身も、ワイン鑑定家として名声を築いていく。1972年にフランスで創刊されたグルメガイドの『ゴエ・エ・ミヨ』は、主たるテイスターのひとりとしてスティーヴンを採用し、その味覚を「シェフィールド産の最高級刃物のように鋭い」と評した。アカデミー・デュ・ヴァンで学び、その後ワイン業界で名声をつかんだ受講生も少なくない。フランス随一のワイン評論家のミシェル・ベタンヌは、前職の国語教師時代に、生徒としてワインを学びに通っていた。のちに世界一ソムリエの栄冠をつかむ、若き日の田崎真也氏も、フランスでの修業時代に短期間ながら、アカデミーの門をくぐった人物だ。
スティーヴン・スパリュアは、その生涯で多くのワイン事業を手がけたが、アカデミー・デュ・ヴァンにはとりわけ思い入れが深かった。パリ時代を振り返り、「自分で言うのも恥ずかしいが、ワインの評価、プロモーション、コミュニケーションにおいて、アカデミー・デュ・ヴァンは、『この街で唯一の存在』だった」と述べているし、「私の人生において、最も誇りに思うのは何かとよく尋ねられるが、いつもアカデミー・デュ・ヴァンの創設だと答える」のだとも、回想録に綴っている。
アカデミー・デュ・ヴァンは、ニューヨーク、スイス、カナダ、ローマ、日本に展開し、ニューヨークとスイス、ローマのプロジェクトは不幸にして短命に終わったものの、日本では健在だ。カナダは一度クローズしたが、近年復活を遂げている。日本校は、1980年に創刊した日本最古のワイン雑誌『ヴィノテーク』の創設者、有坂芙美子氏がパリのスクールでレッスンを受け、スティーヴンとわたりをつけた。東京校の開校は、1987年である。

現在のアカデミー・デュ・ヴァン青山校(東京都渋谷区)
4. 世界を驚愕させた「パリスの審判」 – こぼれ話
1976年5月24日、スティーヴン・スパリュアとパトリシア・ギャラガーは、アメリカ独立200周年を記念して、カリフォルニアワインとフランスワインをブラインドで比較試飲するという、前代未聞のイベント、「パリスの審判」を開催する。当時、カリフォルニアワインは、フランスワインと比べて、品質で大きく劣ると見なされており、誰もがフランスワインの圧勝を予想していたにも関わらず、カリフォルニアが大金星をあげた。仕掛け人のスティーヴンはこれで、サントロペにいた占い師の予言どおり、「永続的な名声」を手にしている。

「パリスの審判」の試飲・審査風景。撮影はスティーヴンの妻、ベラ
世界が震えたこの事件の顛末と後日談については、当ブログ内の別記事に詳述しているので、ここで同じ内容は繰り返さない。こちらを参照してから、また本記事に戻ってきてほしい。
上述の別記事の中で語られていない話を、以下いくつか紹介しておこう。
パリスの審判がワイン界に与えた意義として、スティーヴンは次のようにも話していた。「無名の産地で造られている、知られざる優れたワインが、世に出るフォーマットを編み出した」と。これは後年、チリのエドゥアルド・チャドウィックとともに実施する、「ベルリン・テイスティング」(後述)へとつながっていく言葉である。
パリスの審判を題材に、2本の映画が企画された。1本は完成して上映され、1本はお蔵入りになった。完成したのは、『ボトル・ドリーム』(原題: Bottle Shock / アメリカ公開2008年)という作品で、今でも配信やDVD/Blue Rayで見られる。こちらは、白部門で一位になった、シャトー・モンテレーナのための宣伝映画という趣きの強い作品で(モンテレーナ側は、この映画に1ドルたりとも出資していないと主張しているが)、史実がかなりねじまげられているし、時代考証もいいかげんだ。赤ワイン部門で一位になった、スタッグス・リープ・ワイン・セラーズについては、エンドロール直前のナレーションで一言触れられるだけ。スティーヴン役は、イギリス人俳優のアラン・リックマンが演じているのだが、これが「いけ好かないキザで俗物の中年男」という描かれ方で、「本物」(まだ34歳と若く、道行く人が振り返るぐらいハンサムだった)とは、似ても似つかない。スティーヴンはこのリックマンのキャラクター造形に対して激怒していたし、作品自体も認めていなかった。
かくして、『ボトル・ドリーム』の公開直後から、「史実に基づく、ちゃんとした映画」をもう一本撮ろうという企画がスタートした。1976年の事件発生時に立ち会わせた『タイム』誌特派員、ジョージ・テイバーが著した単行本、『パリスの審判』(原書刊行2005年)を原作に、スティーヴンも協力して脚本制作が始まった矢先、ハリウッドの脚本家の大規模にして長期にわたるストライキが始まってしまう。残念ながら、ストライキが収束した時点で、この企画は立ち消えになっていた。
赤部門の一位となったスタッグス・リープ・ワイン・セラーズの1973 カベルネ・ソーヴィニョン、白部門の一位となったシャトー・モンテレーナの1973 シャルドネの両ボトルは、ワシントンDCにあるスミソニアン博物館内の国立アメリカ歴史博物館において、1996年に永久貯蔵品として登録された。来館者は皆、この伝説のボトル2本を目にできる。スミソニアン博物館はさらに、刊行する雑誌で2013年に、『アメリカをつくった101個のアイテム』という特集記事を発表し、そのひとつしてこのペアのワインが選ばれている。
5. 逆風にさらされつつ、多方面で活躍した1980年代
スティーヴンにとっての1980年代は、手がけてきたあらゆる事業が人手に渡ったり、失敗したりして、最終的には借金生活へと転落する厳しい歳月だった。そんな中にあっても、スティーヴンのワインにかける情熱はいささかも陰らず、後世に残る活動を続けていた。
ひとつは、アカデミー・デュ・ヴァンの名前を冠した書物を、短期間に多数執筆し、刊行したこと。うちの一冊、ミシェル・ドヴァズとの共著である『Académie du Vin Wine Course』からは、ジェラール・バッセMW&MSをはじめとする、未来のマスター・オブ・ワイン、マスター・ソムリエが大勢、学びを得たらしい。本書は1986年に、『ザ・ワイン – アカデミー・デュ・ヴァンのワイン・コース』の名で、日本語版が出版されている(翻訳は、山梨の老舗ワイナリーであるルミエールの前当主、塚本俊彦氏)。
スティーヴンは1980年代前半に、映像の企画にも参加していて、彼がホストとなってフランス全土のワイン産地を紹介するビデオを撮影した。しかし、残念ながらこの作品は、ビデオの規格など諸事情で、世に出なかった。
もうひとつは、師のマイケル・ブロードベントからの要請で、クリスティーズを運営母体とするワインスクールを、ロンドンで1982年に立ち上げたことだ。イギリスでのワイン教育は、1969年に設立されたWSET(ワイン&スピリッツ・エデュケーション・トラスト)が先鞭を付けていたが、高級ワインに絞ってその教育を補完したいというのが、ブロードベントのねらいであった。スティーヴンの指揮のもと、このコースは大きな成功を収め、2016年まで続いた。ちなみに、ブロードベント、スティーヴンともに、のちにWSETの名誉会長職を務めるようになるが、それはクリスティーズでのワイン教育活動が、おおいに評価されたためだろう。
1980年半ばから、スティーヴンは世界各国で開催されるワイン・コンクールから請われ、審査員を務めるようになる。まだまだ、ワインの世界が狭かった時代だから、ニュージーランドといった新興産地でのコンクールでワインを評価する経験は、スティーヴンの見識を広げる結果にもなった。
雑誌にワインコラムを寄稿し始めたのも、この時期だ。ワイン専門誌ではなく、スポーツ雑誌やライフスタイル雑誌だったが、これが後年ワイン専門誌『デカンター』での長期連載につながっていく。スティーヴンは、1962年に創設されたワインライター協会の会員にもなり、のちに会長職も務めた。
経済的に追い詰められていた、この時期のスティーヴンを最後に少し助けてくれたのが、シンガポール航空のワイン選びだった。悪くない報酬がもらえたこの仕事は、1989年に始まり、2014年まで続いた。
6. ロンドンに戻る ~ 『デカンター』との日々と叢書の創設
1990年10月、49歳の誕生日を迎えてすぐ、スティーヴンはロンドンへ戻ってきた。資産と負債を相殺すると、10万ポンドほどのマイナスだったという。まぶしいほどの成功を収め、華やかな舞台で活動を続けた人物にとっては、さぞかし苦い折り返し地点だっただろう。ロンドンではとりあえず、高級デパートのハロッズで職を得たものの、オーナーとの意見対立のせいで、1年も経たずに失業してしまう。コンクール審査員、旅行会社が企画するワイン産地訪問ツアーのガイドといった、不定期の仕事で口を糊する日々が、しばらく続いた。
そんなスティーヴンに声をかけたのが、1975年創刊の古株ワイン雑誌『デカンター』の編集長、サラ・ケンプだった。スティーヴンは、同誌の編集顧問、主席テイスターの地位に就き、1993年9月号から、引退を宣言した2020年4月まで、コラムや記事を書き続け、テイスティング・パネルのリーダーとして、世界中のワインを試飲・評価し続けた。ロンドンのワイン・ジャーナリズムにおける最重要人物として、ありとあらゆるワイン産地から招待を受け、最晩年まで旅を止めなかった。
スティーヴンは、デカンターの名前のもと、世界有数のワイン・コンクールを起ち上げ、これは今日も続いている。かつて、英語圏のコンクールといえば、ロンドンで開かれるインターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)が一強だったが、負けず劣らずの対抗馬を産み出したのだ。スティーヴンは、IWCに範をとった日本のワイン・コンクール、ジャパン・ワイン・チャレンジ(JWC)の共同議長を、1998年から2003年まで務めた経験があり、コンクールをオーガナイズするノウハウをもっていた。2004年にデカンター・ワールド・ワイン・アワーズ(DWWA)を、共同創設者兼会長として立ち上げると、数年で世界有数の規模へと成長させ、2017年までこのコンクールを率いた。出品されたワインの数は、初年度2004には4500銘柄だったが、会長を務めた最後の年2017には1万7000銘柄を超え、世界最大級になっている。香港で開催されるアジア版の姉妹コンクール、デカンター・エイジア・ワイン・アワーズ(DAWA)も、2012年から開催されており、そちらにもスティーヴンは会長として関わった。
『デカンター』誌といえば、毎年一回、ワインの世界に優れた功績を残した人物を選んで表彰する、「マン・オブ・ザ・イヤー」の企画が有名である。これは業界で最も名誉ある「勲章」だと、1984年の第1回から今日まで、長年にわたって界隈でそう認められてきた(2019年以降は、「ホール・オブ・フェイム/名誉の殿堂」と改名)。この賞に、スティーヴンが選ばれたのは2017年。もっと早い時期であってしかるべきなのだが、例によって謙虚なスティーヴンが、「身内びいき」と受け取られるのを嫌い、辞退し続けたのだろうと想像される。

『デカンター』誌の2024年5月号表紙。アメリカの特集号で、写っているボトルは「パリスの審判」で勝利した、シャトー・モンテレーナのシャルドネ1973年 ©Decanter
『デカンター』誌から引退する前年の2019年には、「アカデミー・デュ・ヴァン・ライブラリー」というすばらしい叢書を、スティーヴンは立ち上げた。師と仰いだマイケル・ブロードベントが著し、スティーヴンもぼろぼろになるまで読んだ古典的指南書、『ワイン・テイスティング』の復刻版を皮切りに、優れた書き手による優れた本だけを刊行している。絶版になった古典の復刻版、新しく書き下ろされた産地紹介本のシリーズ、ワイン業界の大立て者による自伝、特定の産地やテーマにまつわるアンソロジーなど、ラインナップはバラエティに富んでいて、真剣にワインに向き合う者なら誰もが手に取るべき良書ばかりだ。スティーヴン自身の回想録・自伝である『A Life in Wine』も、亡くなる前年にこのライブラリーから再刊行された(スティーヴンの回想録は、別タイトルで別の版元から2018年に一度出版されていたが、編集に問題があったため、再編集ののち再発売になった経緯がある)。この叢書は今も、スティーヴンの生前にともに働いていた有能な版元経営者、スタッフたちが、精力的に出版を続けている。

アカデミー・デュ・ヴァン・ライブラリーの数冊。左肩にスクールと共通のロゴマークが入っている ©Académie du Vin Library
7. ベルリン・テイスティングと世界凱旋の旅
2004年1月にスティーヴンは、チリの大手生産者エラスリスの当主であるエドゥアルド・チャドウィックの招待で、ベルリンを訪れた。チャドウィックは、己が手がける最高品質のワインが、世界市場で幅をきかせるボルドー1級シャトーや、スーパー・タスカンといい勝負をするのを期待して、ドイツの首都でブラインドの比較試飲を企てたのだ。チリワインは当時、主要市場にそれなりの量が輸出されてはいたものの、質よりも低価格が期待されていて、メジャー・リーグの選手だとは考えられていなかった。そう、対決の舞台には、「ミスター・ブラインド・テイスティング」、「考えられない結末を招く男」、スティーヴン・スパリュアが必要だったのだ。
そして、同じように予期せぬ事態が出来した。エドゥアルドの手によるチリワイン2銘柄は、ボルドー1級やスーパー・タスカンを抑え、ワンツー・フィニッシュを飾った。1位が、ヴィーニャ・エラスリスの旗艦銘柄、ヴィニエド・チャドウィックの2000年。2位が、エラスリスと加州の雄ロバート・モンダヴィが組んだジョイント・ヴェンチャー、セーニャの2001年。3位以下だったボルドー1級の中には、ラフィット、ラトゥール、マルゴーの2000年という、「偉大な年の大エース」が3本も含まれていたから、にわかには信じがたい結果である。企ての張本人であるエドゥアルド自身が、最も唖然としていたと、スティーヴンはこの劇的な瞬間を振り返っている。
それから10年間、エドゥアルドとスティーヴンは、世界各地を回り、同じ比較試飲を繰り返した。勝利の凱旋という目的もあったが、同じ条件での比較試飲を、違う場所と違う審査員で何度も実施し、偶発性・恣意性を取り除こうとの意図もあった。サンパウロ、リオデジャネイロ、東京、トロント、北京、ソウル、ロンドン、ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス、モスクワ……全15カ国で22回のテイスティングが行なわれ、そのうちの20回で、エドゥアルドのワインはトップ3に食い込んだ。カリフォルニアのときと同じく、今度もマグレではなかったのである。

世界凱旋テイスティングのひとつを、青山のアカデミー・デュ・ヴァンで行なったエドゥアルド(左)とスティーヴン(右)
8. ブライド・ヴァレー・ヴィンヤード – 英国産スパークリングワインへの挑戦
スティーヴンとベラは1987年、イギリス南部に家を購入していた。スティーヴンは、妻ベラの名義で付近に所有する200エーカーの農場の一角に、ブドウ栽培の可能性を感じるようになる。そうして、2008年から2009年にかけ、自身のワインを造るという長年の夢を実現させるべく、10ヘクタールの土地に4万4000本のブドウ樹を植えた。こうして誕生したのが、ブライド・ヴァレー・ヴィンヤードである。
ブライド・ヴァレー・ヴィンヤードは、イギリス南部のドーセット州にある。ここは、温暖な気候と白亜質の土壌で知られ、フランスのシャンパーニュ地方モンターニュ・ド・ランス地区と似た条件を持っている。スティーヴンは、この地でシャンパーニュと同じ伝統的な製法を用い、高品質なスパークリングワインを造ろうとした。
最初の収穫は2011年に行われ、2014年には、シャンパーニュと同じ伝統的方式で造られた、3種類のエレガントなスパークリングワインがリリースされている。初収穫のあと、数年は期待された収穫量が得られなかったが、2018年は申し分ない生育期間に恵まれたので、このヴィンテージからは約6万本のワインを生産された。2019年、ブライド・ヴァレー・ヴィンヤードは、それまでのスパークリングワインに加え、初のスティルワインである「ドーセット・シャルドネ」と、「ドーセット・ピノ・ノワール」をリリースする。 前年(2018年)には、イギリス初のクレマン、すなわち伝統的製法のスパークリングワインより、若干ガス圧が押さえられた泡も、発売していた。
スティーヴンより2歳年上で、同世代を生きた英国ワイン業界の重鎮であるヒュー・ジョンソンは、ブライド・ヴァレーの「冒険」について、次のようにコメントしている。「スティーヴンの泡は、彼の味覚を絵にしたようになりはじめた。すなわち、精密で、強く、洗練されていて、正確。批評家の一生にとって、長きにわたって追い求め続けてきた偉大な作品を、自ら描くほどの幸せがほかにあるだろうか?」
スティーヴンがこの世を去ったのち、ブライド・ヴァレー・ヴィンヤードは、遺された家族によってしばらく経営が続けられていた。そして2023年9月、このワイナリーは、パブ経営者であるアラスデア・ウォーレンと、ワイン商を営むマーク・バンハムのふたりに売却される。新しいオーナーたちはスティーヴンの志を受け継ぎ、高品質な英国産スパークリングワインをこれからも世界に発信していくのだろう。

2016年の来日時、アカデミー・デュ・ヴァン青山校のセラーで、ブライド・ヴァレーのボトルを持って微笑むスティーヴン
9. スティーヴン・スパリュアが愛したボルドーワインたち
ブドウ樹が植わっているところなら、世界の果てであっても出かけていったスティーヴンだが、個人的な偏愛を注ぐ産地はボルドーだった。その一端を示したのが、『ボルドーワイン不朽の名作10選』(初出:2017年発刊の『デカンター』誌付録)という記事だ。「パリスの審判」の結果から、ボルドーを貶めた人物のように非難を浴びた時期もあったが、スティーヴンは生涯この伝統的なワイン産地を離さなかった。
- Château Haut-Bailly, Pessac-Léognan 2009
シャトー・オー・バイイ、ペサック・レオニャン - Château d’Yquem, Sauternes 1988 (jeroboam)
シャトー・ディケム、ソーテルヌ(ジェロボアム瓶) - Domaine de Chevalier, Graves 1941
ドメーヌ・ド・シュヴァリエ、グラーヴ - Château Margaux, Margaux 1985
シャトー・マルゴー、マルゴー - Château Léoville Barton, St-Julien 1989
シャトー・レオヴィル・バルトン、サン・ジュリアン - Château Figeac, St-Emilion 1970
シャトー・フィジャック、サンテミリオン - Château Latour, Pauillac1964
シャトー・ラトゥール、ポイヤック - Vieux Château Certan, Pomerol 1961
ヴュー・シャトー・セルタン、ポムロール - Château Mouton Rothschild, Pauillac 1959
シャトー・ムートン・ロッチルド、ポイヤック - Château Lafite Rothschild, Pauillac 1806
シャトー・ラフィット・ロッチルド、ポイヤック
この10本の最後を飾るラフィットの1806年は、ワインのプロや熱心な愛好家なら必ず一度は聞かれる質問、「これまで飲んだ中で、最も想い出深い一本はなんですか?」に対する、スティーヴンの答えである。1969年秋に、このワインを飲んだときの印象を、スティーヴンは次のように綴っている。「色は褪せていたものの、透明感のある赤、香りはデリケートで赤いフルーツが感じられた。余韻は引き締まっていて、香り高かった。30分後には天に召されていたが、その記憶はいつまでも生き続けた」
なお、少し変えた質問の「あなたが一番好きなボルドーはなんですか?」に対するスティーヴンの答えは、サン・ジュリアンの2級特級格付けであるレオヴィル・バルトンだった。「ほんとうはラフィットなんだけれど、値段が高すぎるから」と、付け加えるところに、彼らしい慎ましさが垣間見える。
10. スティーヴン・スパリュアを偲ぶ声
2021年3月9日、スティーヴン・スパリュアは79歳の生涯を終えた。死因は癌。半世紀以上連れ添った妻ベラと、長男クリスチャン、長女ケイト、そして4人の孫があとに遺されている。訃報に際し、世界中のワイン関係者から、彼の功績をたたえ、人柄を偲ぶ声が多数寄せられた。いくつか選んで紹介しよう。
『デカンター』誌の創刊編集者のひとりで、長く執筆活動を続けるアダム・レッリミアは、亡くなるわずか前に、スティーヴンにインタヴューをした人物だ。訃報記事の中でレッリミアは、「ワインに関するその知識は百科事典さながらで、記憶力も鋭かったが、何よりも重要なのは、好奇心旺盛で寛大な精神の持ち主であったため、世界中のワイン生産者から愛されていた事実だ。文字通り、世界中のどのワイナリーでも歓迎されていた」と、生前のスティーヴンを評している。
『デカンター』誌にスティーヴンを招き入れ、長年にわたって二人三脚で歩んだ元編集長・代表のサラ・ケンプは、次のように追悼している。「伝統産地に対する深い知識と理解。そして伝統産地以外でも、偉大なワインが造られる事実を受け入れられる寛容さ。これらが混じり合って、『デカンター』の編集方針に影響を与えた。おかげで、世界中で起きてきたエキサイティングな発展を、反映した誌面作りができた。彼は『デカンター』の中心人物で、仕事仲間たちから尊敬され、愛されていた」
当代最高のワイン・ジャーナリストであるジャンシス・ロビンソンMWも、スティーヴンと共に旅をし、同じボトルを幾度となく分け合った仲だ。「スティーヴンはこれから、その華やかだった人生よりも、さらに大きな影響をワイン界に与えた人物として認められていくだろう。あれほどの功績を残していながらも、本人があまりに謙虚で礼儀正しくふるまったがために、正しく評価されない危険が常にあった」と、その人柄に光をあてるジャンシスは、かつてスティーヴンをして、「ワイン界の知られざる英雄 Unsung Hero」と呼んでいた。
11. 結び:スティーヴン・スパリュアの人生を貫いた3つのS
スティーヴンは、娘のケイトが2004年に結婚した際、式で次のようなスピーチをした。
「幸せな人生の秘訣は、今から言う3つのSに尽きます。愛する人(Someone to Love)がいて、なすべき何か(Something to do)があり、将来の楽しみ(Something to look forward to)もある」
逝去の前年に再刊行された回想録の最終ページに、スティーヴンは続けてこう書き付けた。
「わが人生が、この3つのSに恵まれていたのは、私のイニシャルが『SS』だったせいかもしれない。妻ベラと出会い、ワイン業界に入った1964年のはじめにはもう、はじめのふたつのSが保証されていた。ケイトからなされた鋭い指摘、『パパ、あなたがいけないのは、“今”にすぐ飽きちゃうところよ』という言葉は、最後のS、すなわち未来を夢見るのがひとつの生き方なのだと、正しく言い当てている」
ワインの歴史に名が残る人物なれど、本人は名声など気にしてはいまい。ワインの世界に未来だけを見続けた、幸せな生涯だった。

2010年、来日時のひとコマ
【主要参考文献】
Spurrier, S. (2020), *A Life in Wine*, Académie du Vin Library
Loftus, S. (1985), *Anatomy of Wine Trade*, Sidgwick & Jackson
『パリスの審判』 ジョージ・テイバー 著(日経BP、2007)
『パリ対決からもうすぐ30年』 立花 峰夫 著(『ヴィノテーク』 2005年8月号掲載特集記事)
『パリスの審判とは?世界を変えたワイン・テイスティング』 立花 峰夫 著(2008)、アカデミー・デュ・ヴァン・ブログ
Spurrier, S. (2020), *Steven Spurrier’s farewell column: Not‘Goodbye’ just ‘Au revoir’*, Decanter
Spurrier, S. (2010), *100 Wines to Try before you Die*, Decanter
Spurrier, S. (2017), *My top 10 Bordeaux wines of all time*, Decanter
Lechmere, A. (2021), *There are three important things in life…*, Club Oenologique
Stimpfig, J. (2017), *Steven Spurrier named Decanter Man of the Year 2017*, Decanter
Lechmere, A. (2021), *Obituary: Steven Spurrier, 1941-2021*, Club Oenologique
Mercer, C. (2021), *Wine world legend Steven Spurrier, 1941-2021*, Decanter
Robinson, J. (2021), “Steven Spurrier (1941–2021)”, JancisRobinson.com
Robinson, J. (2021), “Memories of Steven”, JancisRobinson.com