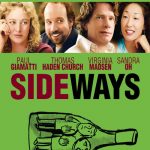前編では、ワイン飲みの悪夢であるブショネ=コルク臭なる悪夢の現象がどのようなもので、何が原因で起きるのかなどなど、ブショネの全体像を俯瞰した。後編では、天然コルク栓に固有のこの問題に対するワイン製造業界のふたつのアプローチ、すなわち天然コルク栓以外の「代替栓」を新たに開発・適用する方向性と、天然コルクの製造工程を工夫することでブショネを根絶する方向性の、ふたつを紹介していこう。
文・写真/立花 峰夫
【目次】
1. スクリューキャップの誕生と挫折
2. 合成コルクとテクニカルコルクの登場
3. 豪とNZがスクリューキャップの楽園に
4. 天然コルクの逆襲
5. おわりに
1. スクリューキャップの誕生と挫折

この小さな植物組織片が、ワインをおシャカにする……
天然コルク栓が普及した17世紀末から数えて約300年の間、有力な対抗馬がない状態で天然コルクがワイン栓の市場を一党支配し続けた。とはいえ、なにせ300年である。当然のことながら、新しいテクノロジーが次々に登場はしてくる。
現在、オーストラリアとニュージーランドの二国において、かつての天然コルクのような絶対的独占の地位を築いているのがスクリューキャップ栓である。ただし、わりあい単純に思われるこの栓が、初めてワインに用いられたのは20世紀も後半に入ってからのことだった。
スクリューキャップの先祖というべき、瓶口にねじをきった気密性に優れたガラス瓶と蓋は、特にワインの容器を想定したものではなかったが、1858年にジョン・メイソンというニューヨークのブリキ職人が特許を取得している(なお、スパークリングワインの瓶内二次発酵・熟成中に用いられる王冠栓も、同じ19世紀後半にアメリカの技術者によって開発された)。
スクリューキャップがアルコール飲料の栓として初めて用いられたのは、スコッチ・ウィスキーのホワイト・ホースにおいてで、1926年のことである。
ワインに適用された初期の例として、当時低価格ワインで有名だったアメリカのガロ社が、1959年から全ラインをスクリューキャップに切り替えたというものがある。その後も、アメリカのバンフィ社がイタリア・エミリア・ロマーニャ州から輸入する弱発泡性の赤ワイン「リユナイト」に、1969年からスクリューキャップ栓を採用し、大当たりを取っている。
しかし、こうした安価・短命なワインに用いられるスクリューキャップとは異なる目的で、製品開発をしていたフランスのアルミニウム企業があった。現在、ワインボトル用のスクリューキャップとしては世界最大のシェアを誇る製品、ステルヴァン Stelvinを開発していたペシネイ社である(その後買収がなされ、現在ステルヴァンはオーストラリアの企業アムコア社の製品)。

ステルヴァンの最新製品、STELVIN INSIDE。
ステルヴァンが商業ベースで初めて採用されたのは1972年、スイスのハンメルというワイナリーによるもので、コルク臭の問題解決がその主目的であった。スイスのワイン業界ではそこからほどなくスクリューキャップ・ブームが起きて、生産量の半分がスクリューキャップで瓶詰めされるようになり、そのシェア拡大は1980年代に入っても続いたのだが、世界的なムーヴメントを起こすにはスイスはあまりにマイナーな産地すぎた。
同じころ、オーストラリアのワイン産業も低品質なコルクに悩まされていた。コルク製造業界は決して認めようとしないが、数百年前からの顧客であったヨーロッパ市場に良質のコルクが回され、オーストラリアのような新興産地には残り物のくずが回されていると同国では信じられていた。
スイスと同じく、スクリューキャップを採用するワイナリーが現れ始め、1970年代の終わりにはヤルンバなど30軒以上のワイナリーが、全部または一部の製品にステルヴァンを用いていた。
しかしながら、この早すぎた「革命」は、オーストラリア国内のワイン消費者の拒絶によって、あえなく頓挫してしまう。安ワインの栓というイメージを覆せなかったのだ。結局、1980年代に入ると、スクリューキャップに転換していたワイナリーも、再びコルクに戻っていった。