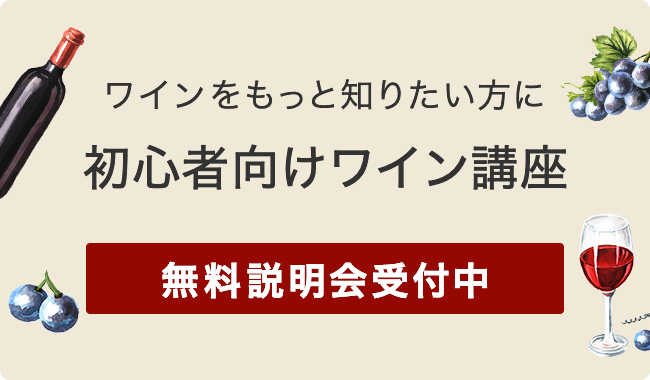世界最難関のワイン資格、マスター・オブ・ワイン。2024年に行なわれたブラインド・テイスティングによる試験では、ギリシャのペロポネソス半島の白ブドウ、モスホフィレロから造られたワインが出題されました。果たして品種と産地が特定できた受験生は何人いたのでしょうか。ギリシャワインと言われて名前が言える白ワインは、せいぜいアシルティコ止まりが普通。一方、最近、とみにギリシャワインへの注目が高まっているのが感じられます。様々な歴史や伝説に彩られたギリシャを、知っておきたい品種と産地に絞って見て行きたいと思います。
【目次】
1. ギリシャの外観
2. 古代の歴史と松脂ワイン
3. 近代の歴史とブドウ栽培
4. ギリシャワインの主要産地と重要ブドウ品種
● マケドニアとクシノマヴロ
● ペロポネソスとアギオルギティコ
● サントリーニとアシルティコ
● エーゲ海の島々とマスカット
5. ギリシャワインのまとめ
1. ギリシャの外観
ギリシャは、沿海部は海洋性の影響も受けますが、概ね地中海性気候。夏も冬も暖かく、冬場でも平均気温は10℃程度と安定しています。ですから、適度に冷涼な影響、例えば高い標高や海風がブドウの生育には重要です。
北部の内陸に向かうに連れて、大陸性の影響を強く受け、夏には30℃を超える一方で、冬場はかなり冷え込みます。
ギリシャの栽培面積は、6万4千ヘクタール。大規模生産者は存在するものの、小規模生産者が数の上では多くて、一所有者当たりの平均栽培面積は1ヘクタールに満たないと言われます。多くの栽培業者が家業を受け継いだか、副収入として農作業をしています。
地中海気候で温暖な産地ですが、白ワインの方が赤ワインよりも多く生産されています。そして、9割方の栽培面積を占めるのが土着品種。綴りや発音含めて名前が難しくて中々憶えられず、ギリシャワインに親近感が持ちにくい理由の一つになっているのではないでしょうか?
白ブドウの最大品種は、サヴァティアノ。中央ギリシャが起源と考えられています。松脂を使ったワイン、レッツィーナに伝統的に使われてきました。干ばつや、かび病に耐性があり、収量も多いので重宝します。中央ギリシャに立地する首都アテネがあるアッティカが主要産地です。
次点は、ピンクの果皮を持つロディティス。歴史の長い品種で、ギリシャ本土とペロポネソス半島で主に栽培されています。名前はロードス島から来ているとも言われます。そして黒ブドウは、アギオルギティコが最大品種です。
原産地呼称に基づく上位格付け。収量等の違いで規定されている最上級、33のPDOとその下位に位置する114のPGIがあります。PDOワインは全体の1割程度と低く、上手く差別化されています。これらの格付け等級の下にはヴァラエタル・ワインという名称が設けられています。産地は表示できませんが、ヴィンテージや品種をラベルに記載可能。そして、それ以外のワインは、グリーク・ワイン(ギリシャ産ワイン)と分類されます。
また、リザーブという名称が付く白ワインは、6か月の樽熟成を含む最低1年間の熟成が条件となります。赤ワインでは、12か月の樽熟成を含む最低2年間の熟成が必要。
2. 古代の歴史と松脂ワイン
ギリシャワインの歴史は、先史時代の紀元前4,500年頃へと遡ります。マケドニアのピリッポイで当時のワイン醸造の痕跡を残す遺跡が発見されました。また、フェニキア人がクレタ島にブドウ樹を持ち込んだとも言われます。そして、クレタ島のミノタウロス伝説を生んだミノア文明と共に、ワインは広がりました。紀元前1,500年前後のペロポネソス半島。ミノア文明を吸収したミケーネ文明でも、ワイン造りを示す遺跡が残っています。
ギリシャはつくづくワインとの絆が深い国。様々な古代の物語にもワインは顔を出します。ギリシャ神話には、ゼウスと人間のセメレの子供、ディオニュソスが、ローマ神話では別名バッカスとして登場。豊穣、ブドウ酒、酩酊の神と知られています。
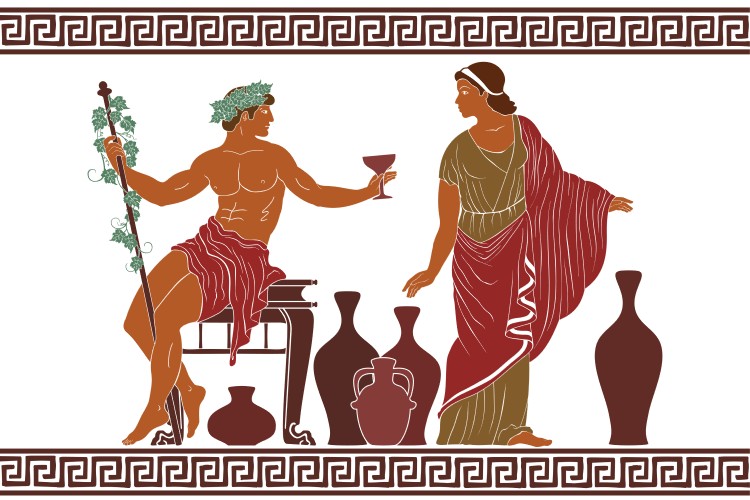
時代がもう少し下った、トロイの木馬の時代。2004年の映画「トロイ」ではブラッド・ピットがアキレスを、オーランド・ブルームがトロイのパリスを演じましたね。この映画の原作とも言える、「イリアス」や「オデュッセイア」は紀元前8世紀の吟遊詩人ホメロスの作とも言われます。そのホメロスは、当時ブドウ栽培が盛んであったことを示す記述を残しています。
そして、ワインは、シンポジアと呼ばれる貴族の社交会で哲学を議論する際にも嗜まれました。水で薄めて飲まれていたようですが、ワインを飲んで哲学を議論するなんて、よほど当時のギリシャ人はお酒が強かったのですね!
ワインが酒でありながら、薬としても重用されていた時代。ワインにハーブやスパイス、花や蜂蜜、松脂も加えていました。古代ギリシャの医学者ヒポクラテスは、解熱効果や利尿効果に留まらず、ワインは傷口への塗布薬としての効用もあると述べました。こうした添加物は酸化を防止し、揮発酸の発生を抑える効果もありました。
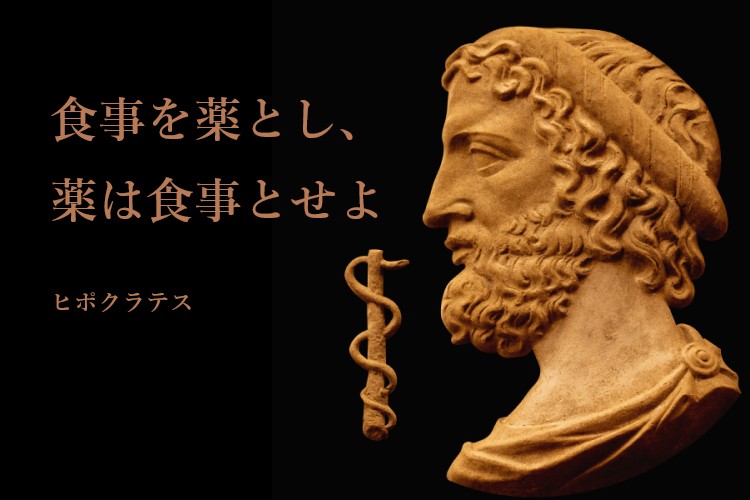
今に続く、松脂を使ったワイン、レッツィーナにも、こうした古代からの歴史が脈々と受け継がれているというわけです。松脂は、古来、ワインの貯蔵に使ったアンフォラの封をするのにも使われました。中央ギリシャのブドウ畑の近辺には松森が林立していたので、ワイン造りに利用するのも自然な流れ。松の木で、できた樽も使われていました。
ローマ時代の農学者コルメラ。様々な松脂の種類を解説しましたが、レッツィーナをご本人は余りお好きでなかったとの説も有ります。古代の昔から必ずしも万人受けするワインでもなかったようです。
イギリスの有名ワイン雑誌『デキャンタ―』が開催する、世界でも最高レベルのワイン品評会のデキャンタ・ワールド・ワイン・アワード。昨年2024年は、2万本近くのワインの内たった50本にしか与えられない、最上位のベスト・イン・ショーにギリシャワインが選ばれました。
その一本が、アシルティコを使ったレッツィーナ。マケドニアのケクリス・ワイナリーの、ティアー・オブ・ザ・パイン・レッツィーナです。レッツィーナは、サヴァティアノが主要品種ですので、品質の高いアシルティコ単一品種を使うのは贅沢です。
ケクリス・ワイナリーは、北部マケドニアに立地しますが、レッツィーナは中央ギリシャが産地としては最も知られています。
このレッツィーナは、地中海地域の松として知られるアレッポマツから取れる松脂を使ったワイン。白ワインの発酵中に松脂が加えられます。特有の香りを付けた後は、松脂は取りさられます。
一般的には、松脂の風味が品質の低いワインを上手くごまかしてくれると考えられる事もあります。でも、ティアー・オブ・ザ・パインは、アシルティコを使った、複雑性に富んだ素晴らしいワインであると高評価。品質の高いレッツィーナは、ブドウの香りを覆い隠すことなく、ギリシャ料理にも合うと言われます。
3. 近代の歴史とブドウ栽培
イタリアには、今でもギリシャのブドウ栽培の歴史が残っています。カンパーニャ州には、エルトリア人の足跡と共に、ギリシャの影響が残り、低い株仕立てが広まりました。プーリア州でもアルベレッロと呼ばれる株仕立ての一種が使われています。シチリアには、紀元前8世紀にはギリシャのワイン造りが到達していたとされています。

東ローマ帝国のコンスタンチノープル陥落後のオスマン帝国の支配。課税対象としてメリットがあったので、ギリシャのワイン生産はしぶとく生き残る事ができました。
1821年にギリシャはオスマン帝国に対して、独立戦争に入ります。独立は叶いますが、ワイン造りは中々軌道に乗りませんでした。それでも、19世紀半ばには、大手ワイナリーが設立され、近代的なワイン造りも始まりました。
その矢先、フィロキセラが発生。19世紀末に、アテネに次ぐギリシャ第2の都市、北東部のテッサロニキで被害が出ました。でも、その後、多くの島を有するギリシャ全域をフィロキセラが覆いつくすことは有りませんでした。
ですから、ギリシャのワイン造りに影響が出るのには時間的な猶予が有りました。その為、ワイン生産はフランスへの輸出等も含めて一時的に増加。しかし結局は、ギリシャでも被害が広がり、ギリシャ本土ではフィロキセラ耐性のある台木を随時導入。それでも、ギリシャの島々の被害は限定的で、遅れて発生しました。1970年代にクレタ島に到達という、他の世界の産地とはだいぶ異なった展開を見せたのです。
20世紀後半に、ブタリやツァンタリと言った大手ワイナリーや、大規模な協同組合が近代化投資を実施。ワイン産業は復興の兆しを見せて、輸出も伸びて行きました。
現在、ギリシャは、農業全般でオーガニックに力を入れています。2012年から2022年迄の10年間でオーガニックの農作地は倍増しています。ブドウ栽培も、栽培面積全体の5パーセントを占めていて、世界のトップ10位に入っています。
4. ギリシャワインの主要産地と重要ブドウ品種

マケドニアとクシノマヴロ
ギリシャ北部の産地マケドニア。35億円の年商規模を持つギリシャ最大のワイン生産者、ツァンタリが拠点を有します。過半が北米や豪州、中国などの輸出市場に出荷されています。同じく、大手のブタリもやはりマケドニア生まれ。半分弱の生産量が輸出に回されています。家族経営で、この産地を牽引して来ました。
この産地は北部に、アルバニア、ブルガリアそして、旧ユーゴスラビアの一部を構成していた北マケドニア共和国と国境を接しています。そして、赤ワイン中心の産地で、主としてクシノマヴロが重要な品種です。
マケドニアには著名なナウサPDOが立地しています。クシノマヴロ単一品種のアペラシオン。マケドニア中部で、山麓部では標高150から350メートルで栽培されています。気候は温暖で、内陸の大陸性気候の影響を受けます。
そして、もう一つ気になるPDOを挙げると、アミンデオンPDOでしょうか。クシノマヴロから造るロゼワインも認められたPDO。北緯40度に立地して、ギリシャでも冷涼地域。標高500から700メートルの高地で栽培が行われ、大陸性気候の影響を受けます。石灰岩や泥灰土から生まれた土壌が見られます。
粘土質が多く低標高で栽培が行われるナウサPDOとは、同じクシノマヴロを栽培しても土壌と気候から異なる影響を受けます。

by Irik – stock.adobe.com
クシノマヴロは、黒ブドウではギリシャのスター品種。主要黒ブドウ品種の中では、最も酸が高く、骨格がしっかりしたワインになります。アントシアニンが低く色合いが薄く、酸もタンニンも強いので、ネッビオーロとよく比較されます。トップのプロたちでもブラインドでこの2品種を見分けるのは、なかなか困難です。また、最近のスタイルでは、早めに飲めるリッチで、タンニンの柔らかいものも。
栽培の観点では、晩熟で、タンニンと糖度を上手くバランスを持って成熟させるのは大変と言われます。病害にかかりやすく、保水性が必要で、石灰質土壌がお気に入り。その一方で、樹勢が強いので適度な水分ストレスも必要です。台木は、乾燥に強いものから、樹勢の中庸なものへと移っているようです。
また、植栽密度にも剪定方法にも好みがうるさいとされています。収量が高いと色合いが益々薄く、タンニンも粗くなるとされています。とは言うものの、香りや味わいを良くしようと、収量を抑える為に、強剪定をすると樹勢が強くなってしまうので要注意。栽培するのは中々大変なブドウ品種なのです。
ペロポネソスとアギオルギティコ
ペロポネソス半島はギリシャ南部に立地。半島と言うよりも殆ど島で、中央ギリシャとは東北部の首都アテナの方向にあるコリントス地峡で繋がっています。中央ギリシャと言えば、映画「スリーハンドレッド」で紀元前480年のテルモピュライの戦いが取り上げられていました。スパルタを中心とするギリシャ軍とペルシャの戦闘が思い浮かびます。
ペロポネソス半島は、山がちな地形ですが、地中海性の気候が中心です。温暖で安定した環境は、気候変動による熱波のリスクにさらされるようになってきています。
ここでは、黒ブドウのアギオルギティコが重要品種。ギリシャでは3,800ヘクタールほどの栽培面積を有しますが、過半はペロポネソス半島のネメアPDOで栽培されています。最近でもさらに栽培面積は増加する傾向を示しています。冬は比較的穏やかで、夏は暖かく乾燥した気候のペロポネソス半島の東部。標高200から850メートルほどの土地で栽培されます。
このネメアPDOを除けば、ペロポネソス半島では、ロディティスから造られる廉価なワインを含めて白ワインが優勢です。
ネメアのアギオルギティコには、伝説があります。ギリシャ神話でヘラクレスが倒したライオン。退治されたライオンはしし座になり、ブドウ樹はその血を浴びたというのです。それで、アギオルギティコは、「ヘラクレスの血」とも呼ばれました。一方で、このブドウの名称の直訳は、「セント・ジョージ」。キリスト教の聖人の、聖ジョージに由来するという説もあります。
早い内から飲みやすいワインも有りますが、10年を超える長熟ワインも。色が濃く、赤系果実にスパイス。滑らかなタンニンを持ち、肉付きが良く、豊かな味わいです。新樽との相性も良いので、メルロに似ているとも言われます。
クシノマヴロよりは育てやすいと言われますが、リーフロール・ウィルス病やうどんこ病などにはかかりやすいとされています。収量は高いので、痩せた土地での栽培が向いていると言われます。
醸造の方に目を移してみると、フルーティーなものは、ポンピング・オーヴァーでタンニン抽出を控えめに早飲みに適したワイン造り。長熟向けにはパンチ・ダウンでしっかりと抽出をする生産者もいます。
その一方で、生産者によっては、パンチ・ダウンの方がソフトな抽出ができると、過剰抽出を避ける為に、ポンピング・オーヴァーをしない生産者もいます。抽出方式だけで、抽出の強さが決まる訳ではなく、実際に手を動かす現場のワイン造りの影響が実は大きいのです。
モスホフィレロとマヴロダフネ
モスホフィレロは、冒頭でご紹介しましたが、ピンク色の果皮を持つ白ブドウ。ペロポネソス半島のマンティニアPDOが、この品種に注力しています。マンティニアは、乾燥していて、病害が少なく、オーガニック栽培が進んだ産地です。アロマティックで、酸にも恵まれた軽快なワイン。温暖なペロポネソス半島の気候とは印象の異なる冷涼さを感じます。
マヴロダフネは、黒ブドウ。ペロポネソス半島のパトラスPDOが有名です。アカイア・クラウス・ワイナリーが、マヴロダフネを使った酒精強化の甘口赤ワインを一躍有名にしました。ポートワインに触発されて開発。大樽で熟成させます。このワイナリーは、ワインツーリズムの先駆けとも評価されています。
サントリーニとアシルティコ

サントリーニ島は、世界中から観光客が美しい日没を目当てに来る島。ギリシャを代表する産地。3,600年前に起きたミノア噴火によってできた、半月形の深さ400メートルを持つカルデラ湾が有名です。

石灰岩と片岩の上に載った、火山灰と砂質の土壌で粘土質が欠如。フィロキセラを寄せ付けません。ところどころに、マグネシウム、鉄分を含む礫や溶岩の堆積物が見られます。
映画「マンマミーア」の風景が、サントリーニ島らしき雰囲気を醸し出しますが、この映画のロケ地はスキアソス島、スコペロス島。サントリーニ島よりは大分、北方に有り、アテネから飛行機で1時間ほど北へ移動した先です。
サントリーニ島では、直近の2025年2月には、群発地震が続いて、非常事態が宣言されました。大勢の住民や観光客が避難しましたが、事態が落ち着きつつあり、少しずつ人々が島へ戻ってきているようです。こうした災害でワイン産業に影響が出る場合は、対処が難しく、我々にできる事は、ワインを進んで購入することくらいでしょうか。著名なワイナリー、例えば、エステイト・アルギロスやドメーヌ・シガラスなどは大丈夫なのでしょうか?
エステイト・アルギロスは、1903年設立の歴史あるワイナリーです。平均樹齢が70年を超える古木に恵まれ、サントリーニでも、最大級の120ヘクタールを超える栽培面積を誇っています。

by wjarek – stock.adobe.com
そして、言わずと知れた島の代表品種はアシルティコ。ギリシャ本土にも栽培は広がってはいますが、何と言っても、サントリーニ島が主要産地。ギリシャの栽培面積の4割程度、約800ヘクタールが集中しています。年間降雨量は、350ミリ程度とは言っても、夏場は全く雨が降らず、灌漑用の水にも事欠きます。これだけ水に不自由しますから、植栽密度も、せいぜいヘクタール当たり、2,500本程度。
温暖なギリシャらしく、アルコール度数は13パーセントを超えるワインが普通。一方、ペーハー値(pH)は3.0前後で、総酸度はリッター当たり6グラム程度です。果実の熟度は高いのに、爽やかな酸が全体を引き締める印象。
海から近い産地ならではの、塩味も感じる事から、スペイン、ガリシア地方のアルバリーニョと対比されます。良く似た輪郭を持った2つのワイン。アシルティコの方が、果実味が抑制されて、厳格さを感じるのと若干アルコールが高いと言われます。また、アシルティコはペーハー値が低いこともあり、ほとんどマロラクティック発酵が行われていないようです。
マロラクティック発酵を起こす乳酸菌は、ペーハー値が3.2程度よりも低いと活動が抑制されます。ですので、酸が高くペーハー値が低い白ワインでは、亜硫酸添加や温度制御で意図的にマロラクティック発酵を止めなくとも、自発的には発酵が起こり難くなるのです。
他方、アルコール発酵は、フレッシュな果実味を残すために、比較的低温な16℃程度でステンレスタンク発酵を行う事が典型的。熟成には、ステンレス、フレンチ或いはアメリカンオークやアカシアと様々な容器が使用されます。
前後しますが、栽培面では、アシルティコは干ばつに強く、様々な土壌に適合。ワイン愛好家に良く知られているのは、バスケット型の特殊な仕立て。クールーラと呼ばれます。

サントリーニ島は、風が非常に強いので、開花や結実に悪影響を与える可能性が有ります。その為、風から守ってくれる、この仕立ては最適。朝霧から湿気を吸収して、水分も蓄えてくれます。風が強く、高温で乾燥したサントリーニ島に見事に適した仕立てです。
とは言うものの、手間暇は普通の垣根仕立てに比べてかなり大変。サントリーニ島以外では、垣根仕立てで長梢剪定されることも普通です。
アシルティコは、ギリシャ以外でも、そのフレッシュでエレガントな味わいから、世界にも広がりつつあります。栽培面積自体はギリシャ全土で2,000ヘクタールほど。ギリシャの中だけで考えても、栽培面積全体の3パーセント程度と決して目立ったものではありません。なのに、特に近年の注目の集まり方は特筆に値します。
オーストラリアではクレア・ヴァレーのジム・バリーや、南アフリカのスワートランドのイーベン・サディがギリシャ外での生産の草分け。消費の観点でも、世界のワイン先進国の愛好家がテイスティングを楽しみ、ソムリエが積極的にワインリストに採用しています。
ヴィンサント
サントリーニ島では、甘口のヴィンサントも伝統あるワインとして珍重されています。18世紀後半にロシアへの輸出で名声を得ます。
ブドウを樹上で過熟させ、天日干し若しくは陰干し。アシルティコを中心にアシリ、アイダニがブレンドされ、残糖が一リットル当たり200グラムを超える、品質の高い甘口ワインが造られます。
イタリアのトスカーナで有名で、もう少し残糖の幅が広いヴィンサントとは、無関係。ギリシャの方は、一語で「Vinsanto」、イタリアの方は、二語で「Vin Santo」と表記されます。イタリアの方は、ブドウ品種にトレッビアーノやマルヴァジアが主として使われ、知名度もギリシャより高いのが現実です。

by slava296 – stock.adobe.com
白ブドウを使うのですが、圧搾しないでそのまま発酵する場合も有ります。そして、最低2年間は500リットルの大樽などでの樽熟成を経て、200から300グラムの残糖を残したスタイルになります。
エーゲ海の島々とマスカット
ミュスカ・ブラン・ア・プティ・グラン。華やかなマスカットなどのトロピカルフルーツやフローラルで華やかな香りを持つ、マスカット系の白ブドウ。ローヌでは、ミュスカ・ド・ボーム・ド・ヴニーズ、南アフリカではヴァン・ド・コンスタンスで有名で、アルザスでは高貴品種の一角を担っています。
ギリシャでは、サモス島やロードス島で、このブドウから素晴らしい甘口ワインが造られています。一般的には、サモス島の方が、品質が高いとも言われます。一方、ロードス島は、フィロキセラの被害を受けていない産地の一つ。高標高の自根のブドウ樹が大切にされています。そして、独立したマスカット・オブ・ロードスというアペラシオンを有しています。
同じエーゲ海にあるものの、かなり北部に立地するリムノス島。ここでは、マスカット・オブ・アレキサンドリアが使われています。一般的には、ミュスカ・ブラン・ア・プティ・グランの方が、品質が高いとされ、陰に隠れた存在のこの品種。ミュスカ・ブラン・ア・プティ・グランと、生食用の黒ブドウ、アキシーナ・デ・トレス・ビアスの自然交配という事が分かっています。
ワインのタイプとしては、「ヴァン・ドゥ」というアルコール発酵初期か発酵前にスピリットを添加した酒精強化ワイン、「ヴァン・ドゥ・ナチュレ」という発酵開始後にスピリットを添加するスタイル、そして「ヴァン・ナチュレルマン・ドゥ」というスピリット添加はせずに過熟したブドウや乾燥したブドウを使ったスタイルが存在します。

by Ralf – stock.adobe.com
残糖は、生産者の造り方により、ケースバイケースですが、イメージとしては、ヴァン・ドゥが最も甘くて、200グラムほど。その次にヴァン・ドゥ・ナチュレが150グラムほど、そして、ヴァン・ナチュレルマン・ドゥが130グラムほどという感じです。
ギリシャの最南部に立地するクレタ島。この島は、ギリシャ神話に登場する怪物ミノタウロスで有名ですね。この怪物が潜むという迷宮伝説の由来ともなっているのが、ミノア文明のクノッソス宮殿。
ギリシャでも最も暖かい産地。でも、900メートの山間部では、冷涼な影響を享受できます。こうした高標高の畑では、高品質なブドウ栽培が行われています。フィロキセラがこの島を襲ったのは、1970年に入ってからと、かなり遅く、折角の古木を随分と失ったと言います。
最も暖かい産地ゆえの悩みとしては、干ばつや山火事の被害。白ブドウは、ヴィラナ、ヴィディアノ。ヴィディアノの古木からできるワインは、干ばつにも強いと珍重されています。赤ワインはコチファリやマンディラリアや、この島ならではの黒ブドウ、リアティコから造られます。リアティコは、この島のダフネスPDOで使われる伝統的な品種。収量は高く、早熟な品種で、樹勢は強いのですが、爽やかで、花やハーブのニュアンスも有り、テンプラニーリョやピノ・ノワールと比べられることもあります。
5. ギリシャワインのまとめ
今回は、古代からの長い歴史を有するギリシャを、古来の伝承も交えながら産地を探訪。代表的な品種やワインに絞って深堀してみました。
普段は、あまり飲む機会のない上級者向けのワインが多いかもしれませんが、世界的な注目を集めつつある産地。どこでも楽しめるわけでは有りませんが、地中海レストランやギリシャ料理店に足を運んでアシルティコやクシノマヴロを楽しんでみませんか?
アカデミー・デュ・ヴァンでも、ギリシャは折に触れて特集を組むことがあります。是非、講座一覧から探してみてくださいね。