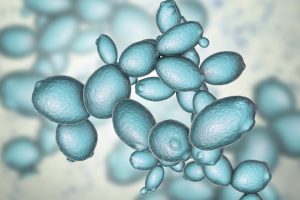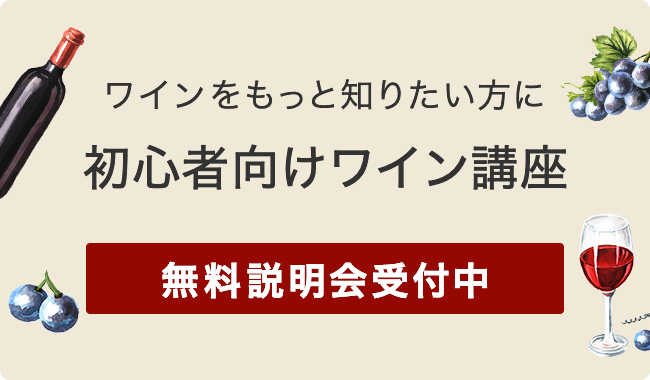神の舌をもつワイン評論家、ロバート・パーカー。ワイン好きならば、老若男女を問わず一度はその名を耳にしているだろう。「ワインの帝王」と呼ばれたこの男の権勢が絶頂にあった2005年、この男についての決定的評伝を世に出したエリン・マッコイは、「あらゆる分野、あらゆる時代を通じて、最も影響力のある評論家」だと断じた。これは、誇張ではない。1980年代から2010年代までの30年間、パーカーは世界のワイン市場を自在に動かす人物であった。パーカーが褒めればワインは売れた。冴えない産地のポッと出の銘柄が、男のお墨付きになったとたん、桁違いの値上がりを見せ、市場から消えた。ただ、この絶対王者によるマーケット支配にも、やはり終わりはやってくる。パーカーが公式に引退を表明し、表舞台から姿を消したのが2019年だ。それから5年が過ぎたいま、パーカー現象とはいったいなんだったのか、前後編に分けてスケッチしていきたい。
【目次 -前編- 】
1. 生い立ちとワインとの出会い
● メリーランド州の片田舎で育つ
● ヨーロッパ旅行でワインと出会う
2. ワインオタクが立ち上げたガリ版刷りのニュースレター
● 1970年代アメリカのワイン事情
● ニュースレター『ワイン・アドヴォケイト』創刊
3. パーカーの独自性と先見性
● 革命的発明となった100点法評価システム
● 濾過叩き:評決のゆくえ
● 天下分け目のヴィンテージ 1982年産ボルドー
● ブルゴーニュという蹉跌
1. 生い立ちとワインとの出会い
メリーランド州の片田舎で育つ
世界一のワイン評論家なら、幼少時からワインに触れ、ある種のエリート教育を受けてきたのだろう、このように想像するのは当然だ。実際、ワイン業界の傑物たちにはそういう育ちの人物が少なくない。アカデミー・デュ・ヴァンの創設者であるスティーヴン・スパリュア、ブルゴーニュの超一級の蔵、ドメーヌ・デュジャックの創設者ジャック・セイス、カリフォルニアの若き天才醸造家モーガン・トウェイン・ピーターソンMWなどなど。しなしながら、ロバー・パーカーはそうではない。彼の世代の平均的アメリカ人と同じく、コーラなどのソフトドリンクを飲んで育った。大学時代にヨーロッパを訪れるまで、一度もまともなワインを口にする機会がなかった。
ロバート・マクドウェル・パーカー・ジュニアが誕生した場所は、1947年7月23日、米国東海岸メリーランド州の大都市ボルティモアの病院だった。メリーランド州は、首都ワシントンD.C.を抱え込むように隣接する。経済的にはアメリカの中でかなり裕福な州で、政治的にはリベラルで民主党支持、いわゆる「青い州」だ。
ロバート・ジュニアの誕生時、両親が暮らしていたのは、ボルティモアから北へと車で30分の郊外にある非法人地域、モンクトンにあった酪農場である。非法人地域とは、市町村といった自治体を持たないアメリカのエリアで、要するにかなりの田舎という意味だ。当時のモンクトンにはひとつだけ小さな食品市場があったが、最も近いドラッグストアは24キロも先だった。今日ではスーパーマーケットもあり、銀行もできたが、人口は5000人程度と、当時も今も少ないままだ。

アメリカ合衆国州地図。東海岸にメリーランド州があり、★印が首都のワシントンD.C.
ロバート・ジュニアは、この田園地帯でハイティーンまで育った。高校を卒業するまで、比較的近いボルティモアの街や、車で90分のワシントンDCまでなら何度か行っていたが、300キロ以上先にあるニューヨークとなると、訪問したのはたった一度きりだった。大学とロースクールに通っていた時期には、モンクトンを離れ都会のボルディモアに住んだが、社会人になってしばらくすると、モンクトンの隣の地域パークトンに家をもって、ボルティモア北部の非法人地域に立ち戻った。ワイン評論家として独立してからもパーカーは、そのキャリアが終わるまでパークトンを離れず、引退後の今もおそらくそこで静かに暮らしている。
他のワイン評論家と比べての、パーカーの特異性は、後述するようにいくつもある。そうした論の陰になってほとんど語られないものの、ワイン産地でも大都市でもない、「ほとんど何もない片田舎」に引きこもっていたのも、実は重要だ。パーカーの生命線でもある「独立性」を、比較的たやすく担保できたのだから。パークトンには、(パーカーとのつながりもあって)趣味としてワインを嗜む人はいただろうが、ワインを職業にしていた人間はパーカー以外にいなかっただろうし、ワインを評論・評価する者など他にいようはずもない。この隠遁者めいた世間との隔離が、この男に神秘的なオーラをまとわせるようになった。
少年時代のパーカーを語るうえでもうひとつ外せないのが、のちに妻となるパトリシア・エッツェルとの出会いである。ふたりは同級生で、十五歳で恋に落ちた。結婚は1969年、パーカーが22歳のときだから、本稿執筆時点(2024年)でもう55年続いた夫婦関係になる。パトリシアは、パーカーがワイン評論家として自立するまで、フランス語の教師として働き、家計を助けたほか、パーカーがフランス語を流暢に操れるようになるまでは、毎年のフランスへの産地訪問に通訳として随行していた。パーカーは、ワイン業界指折りの愛妻家としても知られている。
ヨーロッパ旅行でワインと出会う
高校を卒業したパーカーとパトリシアは、それぞれバージニア州、メリーランド州の大学に進学したが、その一年後にはパーカーもまた、メリーランド大学へと転入してくる。パーカーの人生を変え、のちには世界のワイン市場を変える転機になったのは、1967年のヨーロッパ旅行だった。フランス北東部の町ストラスブールに留学していた、パトリシアを訪ねていったのだ。パリ、ストラスブール、そしてドイツを回った6週間にわたるこの旅行中、パーカーはフランスの食とワインに深く魅せられる。学生のふたりが食事をした店は、カジュアルなビストロがほとんどで、ワインものちにパーカーが評論するような高級品とはほど遠かったが、それでもカルチャーショックは甚大だった。
旅が終わり、大学に戻ったパーカーは、我流のワイン修行を始める。学生仲間とワイン・テイスティングのサークルを結成し、毎月数ドルを出し合ってはワシントンDCの店でワインを買い、皆で飲んだ。ワイン関連の書籍も、手当たり次第読んだ。こうして知識量と試飲の経験値を高めていったパーカーだが、まだワインの味わい、その違いをうまく言葉にする術をもつには至らなかった。表現したかったのは、それぞれのワインの味がどう違うか、それらのワインを買うべきかどうかについてだったのだが、手元の書物にはそうした情報が、ほとんど書かれていなかった。手に入るのは、産地やシャトーのまばゆい歴史や、生産者の伝統的ヒエラルキーといった事柄ばかりだった。
1970年夏に大学を卒業したパーカーは、弁護士になるべく、メリーランド法科大学院に進む。特に法律に興味があったわけではなかったが、この時点ではワインを職業にする選択肢は考えず、大学院進学はある種のモラトリアムだった。大学卒業後、院に入る前の夏休みに、パーカー夫妻は再度ヨーロッパを旅し、このときにはじめて、パーカーが生涯深く結びつくさだめとなる産地、ボルドーを訪問している。
法科大学院時代のパーカーは、熱心でも成績優秀でもない学生だった。唯一熱心に受けたのが、「利益相反(公益と私利の対立)」をテーマにした講義だ。当時のアメリカでは消費者運動がおおいに盛り上がりをみせており、その旗手であった弁護士のラルフ・ネーダーから、パーカーは強い影響を受けた。「製造・流通業界と距離を取り、直接・間接を問わず金銭的な支援を受けず、独立した立場から製品を評価・批評する」という、パーカーのイズムは、ネーダーの活動に範をとっている。
2. ワインオタクが立ち上げたガリ版刷りのニュースレター
1970年代アメリカのワイン事情
1973年夏に法科大学院を卒業したパーカーは、ボルディモアにある農業金庫の職員弁護士として、社会人生活をスタートさせた。大手弁護士事務所のように過酷な労働条件でなかったのが幸いしたのか災いしたのか、頭の中は寝ても覚めてもワインばかり、後の世の言葉でいうところの「ワインオタク」そのものだった。ワシントンDCとボルディモアの双方で、高級ワインを定期的に試飲する会に所属し、ひたむきにグラスの中身と向き合った。
パーカーの生活がワイン色に染まったこの時期、アメリカでは大きなワインブームが起こりつつあった。甘口酒精強化ワインの消費量を、辛口ワインが抜いたのが1968年だ。1947年生まれのパーカーは、いわゆる「ベビーブーマー世代」のはしりで、この世代が旺盛にワインを買い、飲み、のちに米国をワイン消費量世界一の地位に押し上げた。ブーマーたちは、高齢者となった今日においても、米国におけるワイン消費の大きな部分を占めている。
評論・批評を含むワインについての書き物という領域では、イギリスが、アメリカの何歩も先を行っていた。中世の時代から、フランスワインを盛んに消費してきたのはイギリス人なのだから。1970年代半ばには、「ワインについて書く」仕事で収入を得るイギリス人のライター、ジャーナリストが、すでに多数活動していた。ロンドンを拠点にする者が大半だったが、中にはワイン産地に住んでいる者もいた。どちらにも言えたのは、ワインの商取引にも携わっているという点だ。これは、お手盛りの可能性があった、という意味になる。
アメリカのワイン・ジャーナリズムは、まだ産声をあげたばかりだった。とはいえ、大新聞や有名雑誌にちらほらと、定期連載のワインコラムは見られはじめていたし、ワインの専門誌も複数刊行が始まっていて、個人が発行するニュースレター(書店流通網には乗らず、郵便で購読者に配送される定期刊行物)もあれこれとあった。こうした中で、最も大きな商業的成功を収め、現在も継続している媒体が、『ワイン・スペクテーター』誌である。1976年の創刊後しばらくはパッとしなかったが、1979年に元不動産投資銀行家のマーヴィン・シャンケンが買い取って、大成長させた。後年、パーカーのニュースレターである『ワイン・アドヴォケイト』と、唯一張り合えるだけの勢力となったのが、この雑誌だ。
1970年代のアメリカで特筆すべき事件としては、1976年5月に起きた「パリスの審判」がある。この伝説的なブラインド・テイスティングが示したのは、ワインの品質とは「その中身そのもの、内在的な存在」なのであって、ラベルに書かれた名前や、由緒なり伝統なりとは、あいまいな相関しかない、という厳しい事実だった。パリスの審判の教訓、すなわち、何物にもとらわれず、グラスに入った液体だけを純粋に評価すべし、という考え方は、パーカーの道しるべとなった。同時に、ラベルの名前や由緒がアテにならないのなら、「何を指標にワインを買えばいいのか?」という隙間が、アメリカの消費者の内には生まれていた。
ニュースレター『ワイン・アドヴォケイト』創刊
消費者向けのニュースレターを書いてはどうか、というアイデアがパーカーの頭に浮かんだのは、1975年か1976年だという。当初は専業にするつもりなど毛頭なく、ふくれあがり続けるワイン購入費に、この副業の収益をあてるぐらいの目論見だった。たとえ赤字でも、ワイン代を必要経費にすれば、かなりの節税になる。
創刊号のテーマは、1973年産のボルドーワインに決めた。ニューヨークのワインショップなどは、軽めだがフルーティで、早飲みによいと、客にこの年の購買を勧めていたが、パーカーには単に薄く水っぽい、痩せたワインだと感じられた。消費者にこの実情を伝えねばならないと、若きパーカーは義憤に駆られていた。イメージしていたのは、前述のラルフ・ネーダーの消費者運動だった。そのためにパーカーは、自分の媒体は決して広告を取らないと決めた。ワインについても購入代金を払い、生産者や流通業者からどんな便宜を提供されても断るつもりだった。
この広告の不掲載については、今に至るも変わらない不動のポリシーだが、試飲ワインのサンプルについてはやがて、生産者や流通業者からの提供を受けるようにはなっていった。それでも、ワイン産地訪問にあたっての「アゴ足マクラ」、すなわち食費、移動交通費、宿泊費については、パーカーはキャリアを通じて自ら負担し、生産者団体や流通業者の世話にはならなかった。
かくして創刊号、当時の名称で『ボルディモア=ワシントン・ワイン・アドヴォケイト』が、1978年8月に発刊された。浅黄色の紙に、パーカー夫妻自らガリ版で印刷した。モノクロ一色の薄い冊子は、試し読み用の無料号で、ワインショップやワイン同好会から入手した顧客・会員リスト掲載の6,500名にあてて、郵便で送付されている。ロゴマークは、十字軍の十字架を彷彿とさせるコルク抜きにした。この十字架はパーカーにとって、徹底した消費者志向の象徴だった。幸運にも、数百名からの有力購読申込みがあり、第二号の刊行費用はめどが立った。
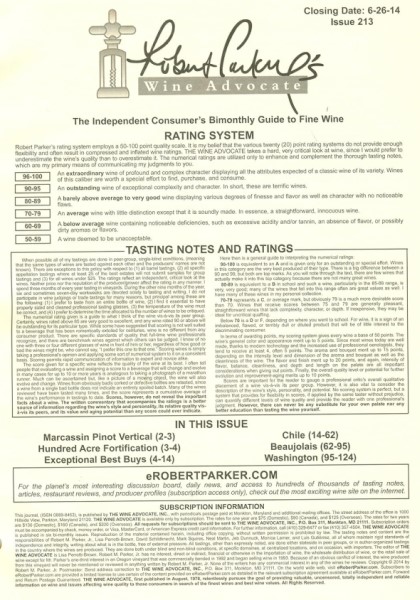
『ワイン・アドヴォケイト』の表紙(2014年発刊の213号)。左上に、十字架をイメージさせるコルク抜きのロゴがある
パーカーは、媒体の構想時に胸に抱き、己に課した消費者との約束を、創刊号できちんと守った。後述する100点満点の採点法で、由緒ある有名な蔵元の数々を、滅多切りにしたのだ。ボルドー左岸の格付け一級、シャトー・マルゴー 1973に対しては、55点という絶望的に低い点数を付けた。「とても薄っぺらで酸っぱく、香りも味もボケていて退屈だ。下手なワインで、買うべきではない」と、試飲コメントも残酷で手厳しい。評価されたボルドーワインは65本で、うち10本は60点以下だったし、80点以上が付けられたのはわずかに3本だった。
「高級ワイン消費者向けの隔月刊ガイド」と銘打たれたニュースレターは、当初は年間10ドルの購読料で、6冊を受け取れるという設定だった。創刊号からその奥付には、次の文章が記されていたのだが、この一文がその後、パーカーの影響力が増大するのを強く後押しした。「媒体ならびにワインの卸商や小売商は、『ワイン・アドヴォケイト』から引用したと明示する場合に限り、掲載されている内容を使用できる」
『ワシントン・ポスト』紙のワインコラムで、パーカー本人とそのニュースレターが取上げられた幸運もあって、購読者は順調に伸びていった。第6号からは、ニュースレター名についていた「ボルティモア=ワシントン」の語を削ったのだが、これは購読者の住むエリアの広がりを受けてだろう。1981年からパーカーは、『ワシントン・ポスト』紙に自らのコラムを寄稿するようにもなる。このコラムでも、自らが試飲して推奨すべきワインについて書いたのだが、点数はあえて記さなかった。ニュースレターの読者だけが、点数を知れるようにしたのだ。この頃にはすでに、『ワイン・アドヴォケイト』を定期購読する酒販店の中に、パーカーの点数を売り場に並ぶワインに添えて貼るところが出始めていた。
創刊号の年からパーカーは、年に2回ボルドーを訪問し、試飲にふけるようになったのだが、これはその後も長年続く習慣となった。その後の数年で、その訪問先は、ブルゴーニュ、ローヌ、北イタリアと広がっていく。副業のワイン評論が、パーカー家の可処分所得・時間の中で、際限なく大きくなっていった。
パーカーが、11年働いた農業金庫での法律職から去り、専業のワイン評論家になったのは、1984年3月である。後述する、「1982 ボルドーによる大躍進」がそれを可能にした。専業になった時点で、『ワイン・アドヴォケイト』の購読者数は9,000人まで増えていた。購読料として得られる収入で、ワイン代や旅行費などの経費をまかない、家族の生活費を含めてペイする採算ラインまで、あと一歩のところだった。
その後も、『ワイン・アドヴォケイト』の購読者数は伸びていき、創刊から20年後の1998年には、45,000人の購読者が、世界35カ国にいたとされる(ワイン百科事典『ジ・オックスフォード・コンパニオン・トゥ・ワイン』の掲載数字)。同じ年には、『ワイン・アドヴォケイト』のフランス語版の刊行が始まった(日本でも、21世紀の初めにごく短期間だが、邦訳版が刊行されていた)。その後、オンライン版の立ち上げ(2000年)、紙版の廃止(2019年6月)と、購読形態の変遷がありつつ現在に至っているが、『ワイン・アドヴォケイト』自体はずっと、購読者数を公表していない。
3. パーカーの独自性と先見性
革命的発明となった100点法評価システム
前項で触れたパーカーの独立性、利益相反を避け、業界ではなく消費者の側に立とうとする姿勢は、当時のワイン・ジャーナリズムでは珍しかった。ただし、パーカーが唯一の存在だったわけではない。同時代のアメリカで、パーカーより少し前から有名になり、パーカーの台頭によって事実上葬りさられたワイン評論家、ロバート・フィニガンも、同じようなスタンスを取っていた。
パーカーによる創案で、ワインの世界を変えたのはやはり、100点満点での採点法であろう。
この男が、100点満点でワインを採点するようになったのは、農業銀行で弁護士として働いていた時代、まだ『ワイン・アドヴォケイト』を創刊する前だ。当時からパーカーは、主催していたテイスティング会の相棒、ヴィクトール・モルゲンロスとともに、飲んだワインに点数を付けていた。しかし、当時の世に出ていたワイン媒体が採用していたシステム、すなわちカリフォルニア大学デイヴィス校が開発した20点法や、星の数で評価をするシステム(満点は五つ星)は、ふたりにはあまりピンとこなかった。それで、編み出されたのが100点法なのだという(最初に思いついたのが、パーカーなのかモルゲンロスなのかは、パーカー自身覚えていない)。1976年までには、この採点法が練り上げられていた。

点数の内訳は、色・外観に5点、香りに15点、味わいと余韻に20点、全体的品質水準あるいは熟成可能性に10点である。合計しても50点にしかならない。そう、100点満点とは言いつつも、実際には50点満点であり、というのもどのワインにも「基礎点」として50点が与えられるからだ(つまり、どんなにひどいワインでも、50点は取れる)。パーカーは50点から100点までをいくつかの点数帯に分け、その「意味」を次のように解説している。
●96~100点
並外れたワイン。深遠かつ複雑な個性を持っており、当該ブドウ品種の最高のワインに期待されるすべての特性を示している。 この水準のワインは、見つけ、購入し、消費するために特別な努力をするに値する。
●90~95点
傑出したワイン。ずば抜けた複雑性と個性を有する。端的に言って、ものすごいワイン。
●80~89点
かろうじて平均以上なワインから、非常によいワインまで。フィネスや風味、個性の水準はさまざまだが、目立った欠陥はない。
●70~79点
平均的なワインで、これといった特徴がほとんどないものの、健全ではある。要するに、素直で無難なワイン。
●60~69点
平均以下のワイン。はっきりとした欠点がある。酸味やタンニンが強すぎたり、風味がなかったり、香りや風味に汚さが見られたりする。
●50~59点
許容できないと判断されたワイン。
このシステムは、恐ろしくわかりやすいという点で、まさに革命的だった。アメリカの高等学校で行なわれるペーパーテストは、100点満点がどの州でも採用されていた。アメリカ人(日本人も)なら誰もが、「97点」と聞けば、小躍りして鼻高々となるし、「56点」と聞けば意気消沈するのだが、この反応はほとんど反射的だ。20点法だと、こうはいかない。「18点」と聞かされても、少し頭の中でカチカチ計算をしてから、「ふむ、なかなか悪くはないようだ」となる。
パーカー自身はキャリアを通じて、「大事なのは試飲コメント本文であって、点数は添え物にすぎない」という主旨の発言を繰り返した。しかし、その点数は本人の意図などまったく介さず、おおいに一人歩きした。90点以上のワインなら飛ぶように売れ、95点以上なら秒殺で売れ、100点満点ならそもそも売り場の棚には並ばないといった具合だ。『ワイン・スペクテーター』など他媒体も、次々とパーカーを模倣し、100点満点の評価を取り入れた。パーカーは、「アメリカのワイン市場で、点数が今のように重要になるとは、まったく考えていなかった。ほかの出版物が多数、私の採点法を真似る状況になるとも思わなかった」とも述べている。
濾過叩き:評決のゆくえ
ワイン評論家やライターが生産者に対し、ブドウの栽培技術やワインの生産技術について、指南するのは珍しい。これはワイン批評に限った話ではないが、餅は餅屋であり、相手の専門領域に踏み込んで口出しをするのは、身のほど知らずの不遜な振る舞いと考えられるからだ。
しかしながら、パーカーは違っていた。瓶詰め前のワインから、微小な固形成分(ときには細菌や酵母といった微生物を含む)を取り除く「濾過」という工程について、猛烈なネガティヴ・キャンペーンを長年にわたって繰り広げたのだ。ブルゴーニュ地方のワイン生産者に対してとりわけ顕著だったが、どんなに高名で評価の高い造り手のワインでも、濾過がなされていると知ったとたん、点数は悲惨なほど低くなった。ニュースレターの誌面でも、当該の造り手に対して濾過を止めるよう、警告を繰り返した。濾過は赤ワインから色を奪うのみならず、美味を構成する成分をも不純物とともに濾しとってしまう。瓶詰めされたワインは魂の抜けた代物となり、熟成もしないというのだ。このバッシングは、ほとんど強迫観念の域に達していて、多くの造り手が「被害」を受けた。叩かれないようにと、実際には濾過がなされているワインを、無濾過だと詐称する者もいた。
パーカーにこの考えを植え付けたのは、1980年代にパーカーと関わりが深かった、カリフォルニア在住のワイン輸入業者兼小売商、カーミット・リンチである。リンチ自身、1980年代末に出版した有名な著書の中で、徹底した濾過叩きを展開し、論争を引き起こした。ワイン・ジャーナリズムの域内で、このリンチ&パーカー連合に、強烈なカウンターパンチをたたき込んだのが、オーストラリア人ワイン評論家のジェームズ・ハリデーである。ハリデーは1992年上梓の著書『ジ・アート・アンド・サイエンス・オブ・ワイン』の最終章で、「濾過は適正に行なえば、ワインに悪影響を及ぼさない」旨の主張を明快にし、この技術の批判者は科学を知らないドグマティストだと暗に示した。ハリデー自身は醸造学のプロではないものの、彼が書いたこの本の技術的な知見については、豪州の高名な醸造コンサルタントであったトニー・ジョーダン博士が監修していた。したがって、ハリデーの主張は、醸造学側の立場を代表する意見だったと見てよかろう。ボルドー大学醸造学部のエミール・ペイノー教授も、1971年の著書の中で、濾過は品質に悪影響を与えないと記している。
この論争について、どちらの陣営の主張が本質的に正しかったのか、答えはグレーである。まず、一口に濾過といっても程度が段階的にある。比較的大きい不純物だけざっくり除去するザルのような方式もあれば、微生物を含め、ありとあらゆる固形物を徹底的に濾し取る方式(クロスフロー濾過)もあり、その中間的なものもある。パーカーやリンチが主張する、濾過の「副反応」は、たしかにフィルターの非常に目が細かくなれば、実際に生じてくるだろう(飲み手が知覚可能な閾値を超えるかどうかはともかくとして)。だが、パーカー、リンチ両名ともに濾過の程度、方式までは論じず、黒白の乱暴な判断をした。品種によって生じる影響の違いもあるのだが、その点もほとんど考慮されなかった。カベルネ・ソーヴィニョンのように強健な品種は、濾過による変化を被りにくいが、繊細なピノ・ノワールは敏感に反応する。
1980年代のブルゴーニュ地方については、時代・土地固有の問題もあった。ブルゴーニュ地方の小規模ワイン生産者のなかには、今も昔も独自の瓶詰めラインを持たず、ボトリング・トラックと呼ばれる移動式瓶詰め業者に頼むところが多い(瓶詰めラインは、ワイナリーの設備の中で最も高額で、ある程度の規模がなければ自前では持てない)。今では事情が変わったようだが、当時のボトリング・トラック業者にはキツめの濾過をするところが多かった。そうした業者に詰めてもらった銘柄が、パーカー、リンチのやり玉に挙げられたのだ。
そもそも、造り手はなぜ濾過をするのか。ひとつには、澱の発生を防ぐためだ。現在では、長い瓶熟成を経た赤ワインに生じる澱は、無害で自然な物質だと知っているワイン消費者が増えたが、一昔前は違っていた。異物混入だと文句を言われたのだ。もうひとつは、生きた微生物が瓶内のワインに残存していて引き起こす、品質不良を食い止めるためである。他国への海上輸送を含め、流通経路で定温・低温を保ち、倉庫での保管時や店頭での陳列時にもその温度がキープできるなら、多少の微生物は悪さをしない。こちらも、今と40年前では事情が違い、客からのクレームを防ぐため、造り手たちは濾過をする十分な理由があった。
どうあれ、世評の面で勝利したのはパーカーだった。「無濾過 Unfiltered」と謳うのは、ワインを売るためのよい宣伝文句になり、それは今日まで続いている。これも、パーカーが「発明」したひとつのコンセプトと呼んでよいだろう。21世紀に入ってから巻き起こり、今もおおいに盛んな「自然派ワイン」のブームにも、この「無濾過=善」という価値観はつながっている。
天下分け目のヴィンテージ 1982年産ボルドー
パーカーにはワイン評論家として、一気にスターダムへと駆け上がった分水嶺があった。1983年の春から展開された、1982年産ボルドーのプリムール販売(先物販売)における評価だ。これはまさに、「運命が微笑んでくれた」瞬間であり、ワイン市場はここから少しずつ、パーカーを中心として回り始める。
収穫翌年3月に樽からの試飲を終えたパーカーは、1982年のボルドー産赤ワインについて、20世紀で最高のヴィンテージのひとつだと確信した。そのワインが瓶に詰められて、市場に出回るのは約2年後になるのだが、パーカーはニュースレターの読者たちに、先物買いで大量入手するよう、情熱的な言葉で説いた。あれこれと長い話を手短にすると、このヴィンテージの秀逸さを声高に説き、長期熟成もすると予言して耳目を引いたのは、ほぼパーカーひとりだった。この点が、天下の分け目になった。
もちろん、シャトー・オーナーたちや流通関係者たちは、希望も込めてその質の高さに期待していたし、フランス人の有力なワイン評論家であるミシェル・ベタンヌも、1929年以来のヴィンテージだと当初から激賞していた。20世紀後半にボルドーワイン全体の品質を多いに高めた、偉大な醸造学者にしてコンサルタントのエミール・ペイノー教授も、今世紀屈指の品質だと認めていた。だが、ワイン批評の世界で大きな力をもつ、イギリス人たちは違っていて、このヴィンテージにかなり大きなクエスチョンを付けた。当時のパーカーがその背中を見ていたアメリカ人ワイン評論家、ロバート・フィニガンも、イギリス人たちと同意見だった。フィニガンは自身のニュースレターに、「試飲したほとんどのワインに、驚くほど失望した」と記したうえで、「頭が悪そう」とまで腐し、「世紀のヴィンテージなどではない」と断じている。『ワイン・スペクテーター』誌も、1978、1979、1981といった先行ヴィンテージを買うよう読者に勧めていた。
識者連中の意見が分かれたのには、明白な理由がある。この年の赤は、当時のボルドーの通例からすると、はるかに熟したブドウから造られていた。仕上がったワインは、豊満で果実味がたっぷり詰まった、劇的な味わいをしていたのだ。渋味も酸味も柔らかかったから、樽に入っていた時分から、すでに飲みやすかった。これは、「若いときは厳めしいタンニンと酸が支配的だが、長い瓶熟成ののちに開花する」という、イギリス人たちやフィニガンの抱く「偉大なボルドー赤」の像とは、相当にかけ離れていた。地球温暖化が進んだ今日の水準から振り返ってみれば、1982はまだまだ、「古典的」なヴィンテージになるのだが、40年前の登場時には、あきらかな異端児だった。
なお、この「濃いワインはどこまで許容されるか?」という問題については、これから約20年後にも、イギリス人批評家のジャンシス・ロビンソン対パーカーという構図でバトルが繰り広げられるのだが、そちらは後編で述べる。
1982年をどう見るかについて、アメリカの小売店は、パーカーの側についた。広告にパーカーの言葉を引用し、旺盛な販売キャンペーンを展開したのだ。ワインは売れた。パーカーの名も売れた。消費者も、最高に美味いと感じられるボルドーを、比較的安値で手に入れられてほくほくだった(2年後に瓶詰め品が出回ったときには、先物買いのときの値段よりかなり高くなっていたし、その後も1982の値段は上がるいっぽうだった)。つまり、パーカー側についた人間は、本人を含めて皆が得をした。「偉大なボルドー」のスタイルを巡る哲学的な論争には決着がつかなかったが、ビジネスの場ではパーカーの圧勝に終わったのである。
ミネルヴァのフクロウを夕暮れに飛ばしてみると、1982年のボルドーでは、極めて重大なパラダイム・シフトが起きたとわかる。新しいパラダイムとは、「濃密で果実味豊かなワイン=善」という考え方だ。この地殻変動を、パーカーが招いたわけではない。地球規模での気候変動(気温の上昇)と、栽培技術の進歩が、「より熟した健全なブドウ」という新たな素材を実現させた。そこから生まれたワインを、ジャーナリズムの分野から熱烈に称賛し、強力に援護したのがパーカーだったに過ぎない。しかしながら、このヴィンテージから約30年のあいだ、「濃ければ濃いほどよい」という新宗教の賛美歌は、パーカーの託宣に乗って自己複製を繰り返し、世界を覆い尽くした。パーカリゼーションと呼ばれたこの現象については、後編で詳述するが、その端緒が「1982 ボルドー」にあったという事実は、頭の隅に置いておいてほしい。
ブルゴーニュという蹉跌
快進撃を続けたパーカーだが、躓きの石がなかったわけではない。ボルドーと並ぶフランスきっての銘醸地、ブルゴーニュでは大失敗をした。原因のひとつは、上述のアンチ濾過キャンペーンである。濾過以外でも、パーカーはブルゴーニュの民の実践について、あれやこれやとあげつらい、名指しで批判した。世界有数のワイン産地といえども、国際的な商いを長年してきたボルドーとは違って、ブルゴーニュはどこまでいっても小農民の群れである。閉鎖的なムラ社会なのだ。「フランス語もろくに話せない、傲慢なアメリカ人」が、あたりをウロウロするのさえ疎んじられるのに、したり顔でワインの味を云々し、素人のくせに造りにまで口出しするなど、許されない振る舞いに決まっている。
こうした不満が凝縮し、訴訟という形をとったのが、1994年に勃発した「フェヴレイ事件」である。フェヴレイは、ニュイ・サン・ジョルジュ村に居を構える大手ネゴシアンで、自社畑も多数保有し、優れたワインを安定して産する造り手だ。フェヴレイのワインは、ずっとパーカーのお気に入りで、ニュースレターでも高く評価していたし、当主であるフランソワ・フェヴレイとパーカーは、同年配で大の仲良しでもあった。しかし、1993年の秋に刊行された『ワイン・バイヤーズ・ガイド』という書物(『ワイン・アドヴォケイト』の内容をまとめて単行本化した書籍)の中で、パーカーはフェヴレイのワインについて、「現地で試飲する味と、フランス国外で飲む味が違う(後者が劣る)」という意味の文章を記した。アメリカの小売店舗の棚に並ぶまでの流通経路、卸業者の倉庫などでの温度管理に問題があるのではないかと、パーカーはそう考えて書いたのだが、疑惑を投げかけられた側は、そのようには捉えなかった。
この文章を読んだフランソワ・フェヴレイは、怒り心頭に発する。フェヴレイは、蔵に来た評論家やジャーナリストには優れた樽のワインだけを飲ませ、瓶詰めしているのは別物なのだと、読者は想像するだろう。パーカー本人と書籍の版元、版元の社長などを、フランソワは名誉毀損で告訴した。ブルゴーニュの民は、フランソワが人格者として尊敬を集めていたのもあって、多くがその味方についた。
結局、訴訟はその年のうちに、和解という形で決着がつく。ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティでその頃、当主の地位にあったオベール・ド・ヴィレーヌが、フランソワを説得し、示談に応じさせたのである。フェヴレイがパーカー側から受け取った慰謝料は、1フランだけだったという。問題は金銭ではなく、名誉だったのだ。
フェヴレイとの訴訟ののちも、何度かパーカーはブルゴーニュを訪問したものの、そこらじゅう敵だらけで、事実上「出入禁止」の状態になってしまう。1996年になると、パーカーは初めての試飲担当助手として雇った、フランス系のピエール・アントワーヌ・ロヴァニに、ブルゴーニュの訪問・試飲を任せた。フェヴレイはしかし、ロヴァニに対しても、蔵への訪問や試飲を断った。
パーカーはそれでも、ブルゴーニュに対して、小さくはない貢献をしている。1990年には、後に邦訳もされた大著 『ブルゴーニュ』も刊行した(この本のフランス語版は、フェヴレイとの訴訟を契機に注目を集め、フランスでかなり売れた)。パーカーの信念、「由緒も伝統もどうでもいい。グラスの中のワインだけを評価する」といういつものアプローチは、ブルゴーニュでも発揮され、小規模な個人生産者が多数、パーカーの後押しでアメリカ市場の綺羅星となった。造り手個人に光を当てるこの手法を、批判する者はいた。ブルゴーニュ在住でワインの商いをしつつ、同地方についての重要な書物を記したイギリス人、アンソニー・ハンソンMWは、「ハリウッド的メンタリティによるスター誕生システム」だと、著書の中で皮肉っている。だが、パーカーがこの土地に持ち込んだ個人優先の批評姿勢は、ブルゴーニュを評価する仕組みとして根付いた。
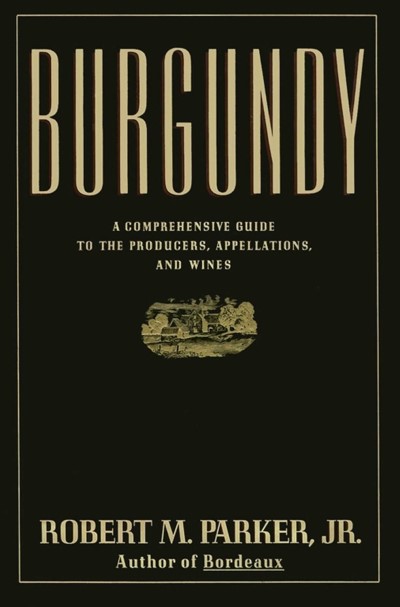
1990年に刊行された、ブルゴーニュについての大著の表紙。邦訳は1992年に出版され、絶版になったあとも長きにわたり、古書が高値で取引された
パーカーは、公式引退後の2020年、インタヴューに答えて、ブルゴーニュで経験した苦い思いを「唯一の後悔」だと振り返っている。「自分は、ピノ・ノワールをそれほど愛したことがないんだ。もし、私がワインを評価する上で、完全に理解できなかったカテゴリーがあるとすれば、それはブルゴーニュだと思う。最も悔やまれるのは、1978年から1993年までのあいだ、ブルゴーニュに対する私の批判がいかに激しく、粗野になりがちだったかという点だ」とも語った。実際、パーカーがこの時期のブルゴーニュに与えた評点は、彼が称賛したスター生産者のワインであっても、他の産地と比べると総じて低く、冷静に見て不当に思われる。ワインの帝王にも、アキレス健はあったのだ。
【主要参考文献】
ロバート・パーカーの著作すべて(『ボルドー』 第1~4版、『ブルゴーニュ』、『ローヌワイン』、『世界の極上ワイン』ほか、未邦訳書を含む)
『ワインの帝王 ロバート・パーカー』 エリン・マッコイ 著(白水社、2006)
Robert Parker Wine Advocate 公式サイト
Perrotti-Brown, L. (2019), *A Tribute to Robert M. Parker Jr.*, Robert Parker Wine Advocate
Woodard, R. (2019), *Robert Parker formally retires from The Wine Advocate*, Decanter
Jefford, A. (2020), *Robert M. Parker Jr extended interview: Decanter Hall of Fame 2020*, Decanter
Kirby, T. (2015), *Robert Parker interview: The world’s top wine critic on tasting 10,000 bottles a year, absurd drinking notes and New World wannabes*, Independent
Wilson, C. (2019), *Michelin Guide buys The Wine Advocate*, Decanter
*Wine Advocate Stake Sold For $15 Million: Report*, (2012), Wine-Searcher