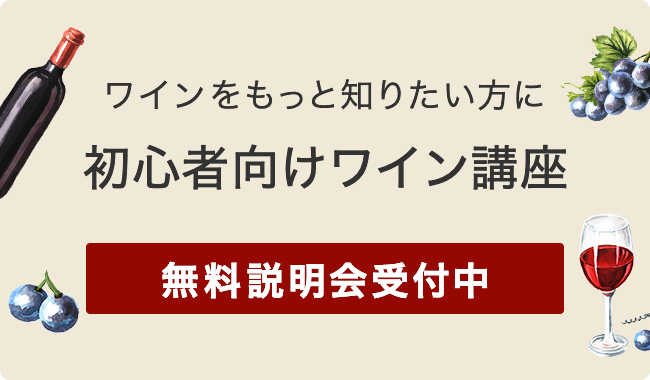「ピュアにして、強烈」。アンリ・ジャイエを1980年に「発見」し、アメリカ市場に初めて紹介した輸入業者、マルティーヌ・ソニエがそのワインを端的に表現した言葉である。低温マセレーションなど、特定の技術で語られがちなジャイエだが、この希代の栽培醸造家が手がけたワインに備わる計り知れないパワー、重層的なアロマとフレーヴァー、そして優雅さとフィネスは、なにか「必殺技」めいた、ひとつやふたつの醸造テクニックに帰せられるものではない。アンリ・ジャイエは、摘まれたブドウの一粒一粒を丹念に吟味した。ワインが樽に入っても安心せず、瓶詰めが終わるまでひとときも気を抜かなかった。この男の「天才」は、ワイン造りのプロセス全体を有機的に組み上げ、髪一本入り込む隙間もないほどの細かさで、チューニングをし続けた点にある。ジャイエが流した汗のすべては、「偉大なピノ・ノワールとは何か」という深い哲学、大きなヴィジョンに基づいていた。だからこそ、この男のワインは、コート・ドールを変え、世界のピノ・ノワールを変え、ひとつの時代を築いたのである。
ワインとは、とにもかくにもブドウ畑で品質が決まるのであり、仕込み以降でこなせる仕事はわずかだと、決まり文句のように言われる。アンリ・ジャイエのような希代の匠人ならば、セラーで己が打ち立ててきた、石碑のごとき巨大な逸物をどう考えたのか。「私が働き始めたころは、ワインの品質とはテロワールが 80%で、人の力が 20%だと思っていたよ。だが今では、50%ずつだと考えるようになった。最高のテロワールから生まれたブドウでも、造り手が悪ければよいワインはできない。だが、悪いテロワールのブドウでも、大変優れた造り手の手にかかれば、まずまずのワインができるのだよ」と、2004年のインタヴューでジャイエは答えている。
5回シリーズで送る本記事、パート3にあたる今回は、アンリ・ジャイエのワイン醸造と熟成について、その革新的だった技術選択を中心に詳述していく。
【vol.3 目次】
4. アンリ・ジャイエのワイン醸造
● ブルゴーニュの「伝統」とは?
● アンリ・ジャイエの醸造法概観
● なぜ完全除梗なのか
● 低温マセレーションの利点
● ギ・アッカド:忘れられたスター
● アッカドの低温マセレーション
● ジャイエとアッカドの小さくて大きな差
● ルモンタージュを多用する合理性
5. アンリ・ジャイエのワイン熟成
● 正しき樽熟成の重要性
● 新樽100%の新しさ
アンリ・ジャイエとは? ~世界で一番高価なワインを造った偶像破壊者
- Vol.1: 宝石より高価なワインに/アンリ・ジャイエの生涯
- Vol.2:アンリ・ジャイエのブドウ栽培
- Vol.3: アンリ・ジャイエのワイン醸造/ワイン熟成
- Vol.4: アンリ・ジャイエが所有・耕作していたブドウ畑
- Vol.5: アンリ・ジャイエの後継者たち/贋作について/まとめ
4. アンリ・ジャイエのワイン醸造
ブルゴーニュの「伝統」とは?
フランスの銘醸にあっては、猫も杓子も、「伝統的なワイン造り」を標榜する。ブルゴーニュもその例に漏れない。皆、自分の手法が昔ながらだと誇らしげに語り、氏素性の確かさを顧客に印象づけようとする。小規模な家族経営ワイナリーが多いブルゴーニュでは、世代間の技術継承が比較的容易ではあるものの、反面、合理主義的な技術選択がなされにくいのも事実である。彼の地のヴィニュロン(栽培醸造家)たちは、己のワイン造りを雄弁に語るが、「なぜそうなのか」という問いに対しては答えを持っていない場合が多い。「父親が、祖父がそうしていたから…」というやつだ。合理的根拠を欠くが故に、自らの手法を「伝統」と称する傾向があるわけで、それらは空虚なイメージでしかない。
ブルゴーニュワインの最高権威のひとりであるアンソニー・ハンソンは、その「伝統」の実体が何であるかについて、著書のなかでさまざまな文献を引きながら、明快に整理してみせた。詳細をここで追いはしないが、一言でいえば時代や地域によって、ブルゴーニュの赤は大きく異なる手法で造られてきたという事実である。おのおのの時代の天候条件、技術的制約、文化状況、そして市場ニーズに適応しながら、ワイン造りは変化してきた。ピノ・ノワールがロゼワインのように仕込まれていた時代もある。また、19世紀から第二次大戦後しばらくまでは、色が濃くフルボディのブルゴーニュが好まれた時代であった。「王のワイン」といったマッチョなイメージは、この時期に形作られたようで、酒精強化ワインに慣れたアングロ・サクソンの嗜好に迎合せんがためのスタイルだったという。しかしここでいう「強さ」とは、実のところ南仏ワインのブレンドによる酒質強化と、極端な補糖によって無理矢理創り出された虚像に過ぎず、ブルゴーニュの長い歴史の中ではむしろ異端でしかない。醸造法はさまざまであっても、ピノ・ノワールの名声とは、柔らかく淡い色の赤ワインとして築かれたのだ。
アンリ・ジャイエの醸造法概観
アンリ・ジャイエが採用する醸造や熟成のメソッドは、別段「伝統的」ではない。極力ナチュラルに、というポリシーと、「伝統的」なのは別である。化学薬品や高度な醸造機器がない時代には、確かに「自然な」ワイン造りはなされていたであろうが、イカサマや怠慢は常に存在した。その時代時代の文脈の中で、いかに高い志を持つかが重要なのであり、古さ自体には特別の価値はない。ジャイエはむしろ、新たな方法を積極的に採用していった。ひとつひとつの手法が、この男の独創というわけではない。高い新樽比率にしても、完全な除梗にしても、ブルゴーニュ全体がその方向を志向し始めていた時だったし、低温マセレーションにしても古くからあった実践の、現代的リメイクに過ぎない。しかし、それらの組み合わせの中で生まれたスタイルは、ひたすらに鮮烈で個性的であった。醸造に対するジャイエのスタンスは非常にアグレッシヴで、経験豊かなハンターを想起させる。
最初に、ジャイエの醸造プロセスを概観しておこう。ブドウは100%除梗する。まれに例外はあるものの、これは作柄によらない。破砕は軽めに留め、粒内での細胞内発酵が多少発生するように仕向ける。この時点で、50ppmの亜硫酸を添加する(当時の水準としては、かなり少なめの量である)。発酵槽に移されたマストは温度調節装置を用いて13~15℃に調整され、4~6日の低温マセレーションを行った後に、アルコール発酵に移る。発酵槽はグラスライニングを施したセメントタンクだ。ジャイエは衛生面への配慮から、木製発酵槽をセメントに切り替えたのだが、この選択の理由として、ステンレスよりも熱の保持が良い点、木製よりも衛生管理が容易な点があげられている。熱の保持が良いと、いずれの段階の温度変化も緩慢に生起する。低温マセレーション中の温度上昇も緩やかであるし、アルコール発酵期間中も、外気温の上下に影響を受けにくく、温度管理装置への依存を抑えられる。果帽管理(キャップ・マネージメント)に関しては、ルモンタージュ(液循環)とピジャージュ(櫂入れ)を併用する(理由は後述)。セニエ(瀉血法)による果汁濃縮は、決して行わない。この技法は結局収量過多に対する安直な対処法に過ぎず、5、6年の瓶熟で欠点が表に現れると、ジャイエは考えるからである。発酵温度は最高34℃まで高められる。ブルゴーニュの中では高温発酵派に入るであろう。キュヴェゾン(アルコール発酵と醸し)の期間は、2週間強(15~20日間)である。この期間についても特に決まりがあるわけではなく、酵母まかせで長くも短くもなる。ジャイエは液抜きのタイミングを、「二酸化炭素の放出が落ち着き、果帽が沈み始めるとき」としている。液抜きの後、プレスワインも加えた上で樽にワインは移される。

収穫されたピノ・ノワールの房。病果がなく健全なのが必須条件である
なぜ完全除梗なのか
除梗の有無およびその比率については、ブルゴーニュでは今もなお、盛んに議論されるトピックである。歴史的には、ブルゴーニュに限らず、すべてのワイン産地で除梗はなされていなかった。特別な理由があるわけではなく、単に技術上の制約からである。その後、近代醸造機器の開発によって、除梗は一般的なプロセスとなった。コート・ドールでは、アンリ・ジャイエが完全除梗の長所を説きつつ大成功を収めたため、1980年代から1990年代にかけて、「完全除梗派」が確実に増えた。
それでも、DRCやルロワ、デュジャックといった大御所で、その時代も全房発酵(除梗をせず、丸ごとのブドウの房をタンクに投入して発酵させる技法)を貫いた造り手はいたし、ほかにも除梗をまったく行わない、もしくは一部に留める生産者はそれなりにいた。単に破砕除梗機が買えないだけという者もいれば、「これまでそうしてきたから」という理由しか持たない者もいたが、果梗の保持に積極的な理由を見出す生産者は、その当時から少なくはなかった。そして、アンリ・ジャイエが引退した21世紀。ブルゴーニュのヴィニュロンたちは、今度は除梗から距離を取り始め、全房発酵が今では大流行である。この、全房発酵の隆盛については、パート5の「9. アンリ・ジャイエの現代性」のチャプターで詳しく見る。
そもそも、なぜ除梗が必要なのか。アンリ・ジャイエは説く。「単純に、果梗はよくない成分を含むからだ。果汁に漬け込むときに悪い影響を与えるのだよ。私も昔は果梗を残していたが、それはブドウが今より小さく、果梗も熟していて、醸造の仕方も異なっていたからだ。わずかだが、果梗が発酵を促進してくれるのも理由のひとつだった。しかし今では、果梗は 100%取り除くべきだと思う」。2020年代の今日まで、「果梗を使うべきか否か?」の論争は、造り手たちのあいだで続いており、先述のように、昨今は全房発酵採用者を含む「果梗利用派」が、「完全除梗派」を凌駕しつつある。後者の主張の論拠である、「果梗はよくない成分を含む」という点について、もう少し詳しく整理しておこう。
まず、果梗のタンニンは非常に青く荒々しいので、例え梗が完熟していても、プラスとはならないという意見だ。これが、除梗を好む造り手たちが最初に述べる意見だが、その他にも果梗の使用がワインにもたらす悪影響は複数あるという。ひとつは、果梗はある程度の量の水分を含むので、除梗をしていない赤ワインは、アルコール、色ともにわずかに希釈するという事実。加えて、20世紀末のブルゴーニュにおいては、果梗の利用がワインの酸味を落としてしまうという、かなり危機的な問題があった。その原因は、化学肥料として大量に畑にまかれたカリウム肥料で(パート2参照)、ブドウ樹の根が吸収したこの元素は、果梗に多く蓄えられる。発酵槽の中で果梗からワインの中に溶け出したカリウムは、酒石酸ほかの有機酸と容易に結合してしまうのである。
低温マセレーションの利点
今日、ブルゴーニュの優良生産者のほとんどが、何らかの形で低温マセレーションを取り入れている。これこそが、アンリ・ジャイエのもたらした革新の中で、最もポピュラーな技法だ。しかし、一口に低温マセレーションといっても、実際には多様なアプローチが存在する。この項では、曖昧になりがちなこの技術の定義とバリエーションについて、多少の整理を試みよう。
まずは、用語の定義から。低温浸漬、発酵前浸漬、コールド・ソーク、コールド・マセレーション、マセラシオン・アフロワなど、いくつかの異なる用語が日本語の文献においても存在するが、それらに決まった使い分けはない。ここでは(アンリ・ジャイエの技術を指す上で)最も一般的と思われる「低温マセレーション」という用語を使う。この用語を簡単に定義するならば、アルコール発酵の開始前に一定期間、果汁と固形成分(果皮・種子など)とを接触させる技術、となる。「低温」という文字の通り、その期間中マストは、ドライアイスや温度管理装置を用いて冷却されるのだが、これは発酵の生起を食い止めるためである(温度が低いと、酵母が活動しにくくなる)。ただし、そのヴァリアントの中には、特別な温度管理を行わないパターンも含まれるので、「発酵前浸漬」という用語のほうが、より広い射程を持つだろう(詳細は後述)。この技術の目的は、いうならばただひとつであり、果皮から良質の成分を抽出することである。アルコールに頼らない抽出のほうが、より良い色、より純粋な果実風味、より洗練されたタンニンが得られるというのが、この技術を用いる造り手たちが主張するところであり、繊細なピノ・ノワールに適した方法であるとされる(ただし、今日この技術は、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、シラーといった品種でも、ごく普通に用いられている)。
ギ・アッカド:忘れられたスター
低温マセレーションという技法がブルゴーニュで注目されはじめた1980年代、アンリ・ジャイエ以外にもうひとり、有力な提唱者がいた。いまでこそ忘却の淵に沈んでしまったが、往時はジャイエに比肩しうるほどの名声、または悪名を誇った人物である。その名を、ギ・アッカドという。
ギ・アッカドはレバノン出身の醸造技術者であり、1975年にニュイ・サン・ジョルジュ村で、ワイン造りについてのコンサルタント業を始めた。1980年代のピーク時には、契約する蔵は40を数えたが、少しずつ顧客を失っていき、1990年代半ばにはブルゴーニュから姿を消してしまった。アッカドが助言していた蔵の中には、ジャン・グリヴォやクロ・ド・タールといった伝統ある名家も含まれてはいたが、中心となっていたのはコンフュロン・コテーティド、ペルナン・ロッサンといった、それまで無名であった造り手である。彼らは、今でこそ独自の道を歩み、優良生産者としての地位を築いているが、世に出るきっかけはアッカドのコンサルティングだった。アッカドという人物は、活躍していた頃でさえ、一体どこで何をしていたのか、謎に包まれた部分が大きかった(そしてそののち、どこへ消え、今どこにいるのかは誰も知らない)。ボルドー大学の故デュブルデュー教授と関わりがあり、教授が提唱したテクニック、白ワインのスキン・コンタクトにヒントを得たというのは、時折耳にした噂だが、真偽のほどは定かでない(アンリ・ジャイエは、「アッカドは自分からヒントを得た」と述べているが、こちらの真偽も同様である)。
アッカドは、当時の時代背景を踏まえ、高潔な目標を掲げた人物でもあった。「フィロキセラ前の本物のブルゴーニュワインを、長い寿命を持つそれを再現する」というのだ。醸造コンサルタントとしての顔ばかりが強調されるが、アッカドは栽培面でも重要な提言を行っていた。彼は、アンリ・ジャイエと同じく、過剰なカリウム肥料投入の弊害について、最初に告発した人物のひとりである。また、ワインの味わいを強くしつつ、なめらかな口あたりを出すのを狙って、植樹本数の増加(ヘクタールあたり1.25万本)、収量の低減、遅摘みによる超熟(≠過熟)の果実を、三つの柱とした。これら畑での実践の真っ当さに対し、異を唱える人間は少数派であろう。
アッカドの低温マセレーション
議論を呼んだのは、アッカドの醸造法のほうであった。ブドウは一部除梗・破砕された上で、発酵槽に移される(除梗比率は顧客により異なり、おおむね50~75%だったが、アッカド自身は100%の除梗を推奨した)。発酵生起を回避するため、温度管理装置を用いてマストを5~15℃の低温に保ち、その状態で5~10日間浸漬を行う。この際、通常の2~3倍の量の亜硫酸(100~150ppm程度)が添加されるのだが、この多量の亜硫酸添加の狙いはふたつある。ひとつは温度管理と同じく、発酵開始の遅延である。アッカドがコンサルティングを始めた当初、顧客の中には温度管理装置を持っていない者も多く、そうした顧客の仕込み場では、亜硫酸で酵母の動きを止めるのが必須であった。もうひとは、亜硫酸のもつ抽出効果である。亜硫酸には色素溶出を促進する働きがあり(ただし大量に添加しなければその効果は薄い)、ピノ・ノワールについて色の濃度を重視していたアッカドにあっては、この効果は非常に重要であった。その後のプロセスは、比較的穏当である。発酵はゆっくりとスタートし、その温度は30℃以下に抑えられる。アルコール発酵の終了と同時に液抜きはなされ、発酵後浸漬はまったく行われない。プレスワインも添加される。亜硫酸は、発酵槽へのブドウ投入時に加えられた量がすべてであり、そのあとは樽熟成中も、瓶詰め前にも追加されない。
アッカドのワインは、市場に登場してまもなく、熱烈な賞賛を与えられたが、辛辣な批判も同時に巻き起こっていた。攻撃されたポイントは二点あり、まずは亜硫酸の添加量の多さである。過度の亜硫酸添加は、ワインの味を固くフラットにする。アッカドは、瓶詰め後の段階での総亜硫酸量は、自分のワインも他の生産者のワインもそう変わらないと反論していて、上述の数字が確かならば、それはその通りであろう。当時の文献を見る限りは、テイスティングで明確な差が感じられるほどの影響はなかったようである。また、アッカドの顧客であった生産者たちが、温度管理装置を導入するにつれて、現実に亜硫酸添加量が減少したという経緯もあり、事態は判然としなくなっていった。もうひとつの攻撃ポイントは、熟成能力およびスタイルに関する批判である。批判者は、アッカドが関わるワインについて、「コート・ロティのような色・風味で、ブルゴーニュらしくない」、かつ「どれも同じ味で、アペラシオンの個性がない」とこき下ろした。こうした批判に対してアッカドは、「10年も熟成すれば、各々のアペラシオンの個性が現れる」と反論していた。
アッカドの主張は正しかったのか。ブルゴーニュワインの最高権威のひとり、レミントン・ノーマンは1996年刊行の著書の中で、アッカドの仕事について詳述したうえで、そのワインは立派に熟成するし、熟成すればテロワールの個性が現れると、肯定的な評価をしている。日本を代表するワイン研究家の堀賢一も、2007年刊行の著書の中で、ノーマンとほぼ同じ意見を述べており、10年、20年の瓶熟成という時の試練に、アッカドのワインは充分耐えたようである。その判決が下るまえに、アッカドがブルゴーニュを所払いされたのはなぜなのか。これまたブルゴーニュワインの最高権威のひとりであった、故クライヴ・コーツは、「アッカドの最大の敵は、彼自身」だと述べたうえで、この男の秘密主義が根拠のない誇張を生み、クライアントとの付き合いも下手であったと記していて、どうもそのあたりに問題の根がありそうだ。
ジャイエとアッカドの小さくて大きな差
アンリ・ジャイエが用いる低温マセレーションも、表面的にはアッカドの手法とほとんど同じである。目立った違いは、ジャイエのほうが亜硫酸の添加量が少ない点ぐらいだろう。しかし、この技法に向き合う姿勢の面において、両者が似て非なるものではないかと、ワインライターのパトリック・マシューズは次のように問題提起をした。
「……誰もが同意する事実だが、ジャイエは果梗によるボディ増強に頼らずに強烈なワインを造る。ジャイエは低温マセレーションを用いているのか。もしそうだとして、アッカドなら必要とする多量の亜硫酸添加をどうやって無しですませているのか。この件については、さまざまな人間がさまざまな説明をしている。ロイ・リチャーズ(訳注:イギリス人有力ワイン商)は、ジャイエは発酵に先立つ浸漬、いわゆる低温マセレーションを行っていないと述べる。アンソニー・ハンソン(訳注:ブルゴーニュ専門のイギリス人有力ワイン商兼ライター)は、逆の意見である。4日から5日、発酵タンクの温度を15℃に保ち、色の抽出が終わった後、最大34℃まで温度を上昇させる、このようにハンソンは説明する。ジム・クレンデネン(訳注:アンリ・ジャイエに師事したカリフォルニアのワイン生産者)によればこうである。『アンリは、朝まだ涼しいうちに収穫する。彼の発酵タンクは納屋にあるセメント製で、暖まるまでに5日はかかる』。ジャイエ自身は、ライターのジャッキー・リゴーに次のように話している。『ブドウは4日から6日、発酵前に浸漬する。収穫期間中涼しいと、発酵が始まるまで長い時間がかかり、結果ワインがフルーティになると気付いたからだ。その上、いつも良い色が出る。温度管理装置を用いれば、たとえ収穫時の気温が高い年でも同じ環境を産み出せる。そうすれば、ワインは同じようにフルーティで、複雑で、そしてバランスの取れた味わいになる』
事実はおそらくこうであろう。前述の人々は、ジャイエのテクニックの異なる面を伝えていただけなのだ。収穫時の気温が高いか低いかによって、それは変化するのである。大切なのは、ジャイエが自然な流れを改良しようとしたのではない点だ。彼は、望みうる最良の自然な環境を、技術の力を借りて再現しようと試みたのである。この冷却技術は、シャプタリザシオンに比してよいかも知れない。シャプタリザシオンとは、発酵の最終段階で糖分を添加する技術で、ナポレオンの農業大臣であったジャン・アントワーヌ・シャプタル(1756-1832)によって提唱された。シャプタリザシオンもまた、広く悪用されている技術のひとつなのだ。悪用といった場合、それは過大な収穫量がもたらす結果からの逃げ道として用いられる。結果とは、十分な糖分や風味のないブドウが実ってしまう事態だ。
しかしシャプタルは、次のような考えから自然なワイン造りへの介入を勧めたのだった。シャプタリザシオンとは、『もっと作柄が良ければ望めたであろう環境を実現する』ための技術であると。この、一見些末に思われる差は極めて重要である。ワインが持つアルコールや酸、抽出物が、自然に得られたのか、もしくはワイナリーでの人為的操作のみに基づくのか……」
引用にもある通り、その差はまことに微妙である。アッカドもまた、ジャイエと同じく、自然なワイン造りを追求する醸造家のひとりであった。技術と自然の狭間で、わずかにさじ加減を間違えたのが、転落人生のはじまりだったのか、そのあたりは正直よくわからない。2004年のインタヴューでアッカドについて尋ねられたジャイエは、面識がなかったと前置きしたうえで、亜硫酸添加量の多さやマセレーション温度の低さについて辛口極まりないコメントをしており、「アッカドと私のやり方の違いをあげるとすれば、やはり自然に仕事をさせるか否かになる。私は自然に主導権を与える。発酵前に、 13 ℃までマストを冷やすだけだが、もしブドウがはじめから冷たければ、あえて冷やしたりはしない。アッカドの場合、大きく人間が介入する。自然の代わりに奴が主導権を握るのだ」と、締めくくっている。いずれにせよ、事実としてあるのは、2024年現在、アンリ・ジャイエのリシュブール1985年には、800万円を超える値段が付いているのに対し、アッカドの上顧客のひとりであったジャン・グリヴォのリシュブール1985年は、33万円で買えてしまうことだ(ふたつのワインの価格は、ワインの市場価格検索サイト 「ワイン・サーチャー」による)。

自身の醸造テクニックについて、雄弁に語るアンリ・ジャイエ(2004年)
ルモンタージュを多用する合理性
一般論として、ピノ・ノワールについては果帽管理のテクニックとして、ルモンタージュよりもピジャージュを用いる造り手が多い。これまた一般論でしかないが、ルモンタージュよりもピジャージュのほうが、タンニンほかの成分抽出が強めになる傾向がある。もともと果皮に含まれるタンニン量が少ないピノ・ノワールという品種では、それゆえピジャージュが好まれるというのが、教科書的な説明である。とはいえ、これはかなり乱暴な議論で、ルモンタージュであれ、ピジャージュであれ、一日に何度行なうか、一回につきどれだけの時間行なうかによって、抽出度合いは変わってくるし、ルモンタージュの場合は、ポンプの速度がどれぐらいか、ホースの口径がどれぐらいかなど、さらに変数は増える。そうした留保がつくのを承知したうえで、アンリ・ジャイエがタンニンの抽出を抑えようとしていた点、そのためにルモンタージュを主に用いていた点について触れておきたい。
ジャイエは、2004年のインタヴューでこのように語っている。「私は若くして働き始めた。いつも好奇心旺盛で、よくブドウ樹を観察していたから、いろいろと気付いた。当時のブルゴーニュでは、タンニンの強すぎるワインが多かった。タンニンがワインの寿命を延ばすと誤解されていたからだ。本当は、アルコールとタンニンと酸の三つの要素のバランスこそが、ワインに長寿をもたらすのだよ。私は若いときでも美味しく飲め、さらにそこから良くなってゆくようなワインを造ってきた。ブルゴーニュのワイン造りのヴィジョンを変えたのは私なんだ。今では若い世代の造り手の多くが、私と同じように考えている。タンニンが少なめで、重過ぎないワインを造るという意味だ。ピノ・ノワールの魅力とは、豊かな香りと複雑な味わいなんだが、タンニンが強すぎるとそれが全体を覆ってしまう。大切なのはバランスなのだよ。今主流になっているのは、ピジャージュを少なくしてタンニンの抽出量を減らすようなワイン造りで、それによってエレガンスや香りが取り戻されたんだ」
ジャイエの果帽管理は、キュヴェゾンの期間中のほとんど(5分の4)はルモンタージュであり、朝と夕方の一日二度、30分ずつポンプを回す。ピジャージュに切り替えるのは、発酵中のマストの比重が1010から1000になったあと、最後の3、4日のみで、一日に一度か二度、果帽が液中に押し沈められる。ただし、このあたりはヴィンテージによって柔軟に組み替えられていて、たとえば果皮が優れたタンニンを豊富に含んでいた1983年には、ピジャージュはほとんど行われなかったという。ジャイエは、ルモンタージュに重きを置く理由を、次のようにも説明している。「種子が果肉から外れてほしくなくてな。外れた種子がタンクの底に溜まってほしくないんだよ。そうなると直接種子が果汁と触れ、タンニンの量が多くなりすぎるからね。種子ではなく、果皮のタンニンが欲しいんだ。果皮のタンニンを抽出したほうが、ワインはエレガントで繊細になる

発酵中のピノ・ノワール。ポンプとホースで液を循環させるルモンタージュの作業
5. アンリ・ジャイエのワイン熟成
正しき樽熟成の重要性
「ブルゴーニュの赤の80%は、マロの前まではよく出来ている。しかし、瓶詰め後にまともなのは、たった20%しかない」
1985年にアンリ・ジャイエが発した言葉である。当時はまだ、いい加減な熟成管理が原因で損なわれてしまうワインが多く、それがこの男を苛立たせていた。樽熟成中の捕酒の不足による酸化、不十分な衛生管理による微生物汚染といった、基本的な欠陥の回避さえ出来ない生産者を、ジャイエは厳しく断罪した。こういった生産者たちは往々にしてワインの試飲すら怠っていたため、問題の発生に気付かず、被害が拡大していたのである。またジャイエは、返す刀で過保護な臆病者を斬るのも忘れなかった。過大な量の亜硫酸添加、過度の清澄・濾過など、ワイン造りに伴うリスクを極小化しようとするアプローチもまた、杜撰さと同列に置かれていた。2024年の今日、ブルゴーニュで造られるピノ・ノワールの大半が、ジャイエが言うところの「よく出来ている」ワインになった背景には、教育者としてのこの男の貢献が確実にある。
「ワインが自然に生まれ出るようにしてやる」というジャイエのアプローチは、熟成から瓶詰めまでの過程でも変わらない。キュヴェゾンを終えてタンクから抜かれたワインは、プレスワインも加えられた上で、容量228リットルの小樽に移される(ピエスと呼ばれる、ブルゴーニュ地方のワイン生産者が標準的に使うサイズの樽である)。新樽比率は、村名格以上の銘柄はすべて、作柄によらず常に100%。樽材の産地は中央フランスのアリエおよびトロンセで、樽材の内側の焼きはミディアム・トースト、樽製造業者はフランソワ・フレール社、人呼んで「ブルゴーニュ樽のロールス・ロイス」という贅沢品だ。マロラクティック発酵は樽の中で自然に生起させる。樽やセラーを暖めて、乳酸菌の活動を促進したりはしない。樽内での熟成は平均18ヶ月で、その期間中は、不要な酸化や有害微生物の繁殖を防ぐために、かなりの頻度で補酒をする(樽入れしてすぐは3、4日おき、やがて一週間に一度、その後は必要に応じて)。熟成期間中を通じ、5回の化学分析が実施される。樽から樽への澱引きは2回で、一度目はマロラクティック発酵の完了時、すなわち樽入れから8~10ヶ月が経過した時点で、二度目は瓶詰めが近づいてきた頃である。今日のブルゴーニュでは、澱引きを一切行なわない造り手も少なくないが、ジャイエの時代は3~4回の澱引きが普通だったから、2回は少なかった。ジャイエが澱引きの回数を抑えていたのは、亜硫酸の添加量を減らしたかったからである(澱引きをすると、かなりの量の酸素がワインに取り込まれるため、遊離亜硫酸の量が減り、ワインを酸化から守るためには亜硫酸を追加する必要が出てくる)。清澄については、当初は一樽あたりふたつの卵白で清澄していたが、1990年以降は無清澄になった。瓶詰め前の濾過は行なわず、少量(13ppm)の亜硫酸を追加したのち、樽から直接手詰めで、ボトルにワインを注ぎ入れる。「ふたつの口をもつ山羊」という名の器具(蛇口の先が二股に分かれた古めかしい瓶詰め道具で、樽の鏡面に差しこんで使う)を使って、一日に5樽――1樽あたり2時間をかけて、というのがジャイエのペースであった。手詰めのワインは、ボトルシックと無縁だとジャイエは主張する(「ボトルシック bottle sick 」とは、瓶詰め直後のワインの風味が、一時的に平板で閉じた状態になることで、「ボトルショック bottle shock 」とも呼ばれる)。

228リットル容量の樽が並ぶブルゴーニュ地方のセラー
新樽100%の新しさ
ブルゴーニュで新樽の使用比率が向上し始めたのは、1980年代の前半、つまりアンリ・ジャイエが世に出た時期とほぼ一致する。それまで、ブルゴーニュでは、樽の新しさに特別の価値が認められてはおらず、老朽化した古樽と交換する形で、新樽が用いられるに過ぎなかった(15%程度が、当時の標準的な新樽比率だった)。しかし、ボルドーなどの他産地で、新樽の使用がブームとなり、同時にブルゴーニュの生産者たちにも経済的な余力が生まれてきたため、状況が変わり始めた。
衛生上のメリット(有害微生物による汚染が起きにくい)、重合の促進による色の安定化とタンニンの口あたり向上(酸素透過量が多いため)、そして樽材がワインに付加する好ましいさまざまな風味とタンニン、これらが新樽熟成の効果である。品種を問わず長熟タイプのワインにとって、新樽がよい結果を生みやすいのは、大ざっぱな議論では疑義のないところであろう。重要なのはその比率が「適度」か否かだ。繊細なタッチがその持ち味であるピノ・ノワールにおいて、樽材から抽出される特有の風味やタンニンが、のさばりすぎるのを歓迎する醸造家はいない。新樽比率は積極的に低くすべきという造り手もいるが、最終的には果実味の強さと樽風味のバランスであり、X%という数字にはあまり意味がない。
アンリ・ジャイエは、ワインのバランスが適正であれば、たとえ成熟度の低いヴィンテージですら、新樽100%に耐えうると考えていたと、レミントン・ノーマンは記している。たしかに、ジャイエのワインは力強さにおいて群を抜いていたから、「新樽は問題でない」と考える飲み手が大多数だった。しかしこれとて、皆が賛成している訳ではない。クライヴ・コーツは1997年刊行の著書の中で、「時折、アンリ・ジャイエのワインはオークが強すぎる」と批判した。コーツ曰く、樽材由来のタンニンはブドウ由来のタンニンと異なり、瓶熟成を経ても柔らかくならないという。よって、経年変化によってフレッシュな果実味が後退すると、フルーツとオークのバランスが崩れ、荒々しいタンニンが前面に出てしまうというのが、コーツのお気に召さなかった「新樽の副作用」だ。コーツは、ジャイエの後継者である甥のエマニュエル・ルジェが、軽いヴィンテージには新樽比率を減らすようになったと述べ、賢明な選択だとコメントしている。
【主要参考文献】
『ヴォーヌ・ロマネの伝説――アンリ・ジャイエのワイン造り』 ジャッキー・リゴー著(白水社、2005)
『アンリ・ジャイエのブドウ畑』 ジャッキー・リゴー著(白水社、2012)
『ほんとうのワイン――自然なワイン造り再発見』 パトリック・マシューズ著(白水社、2004)
『最高のワインを買い付ける』 カーミット・リンチ著(白水社、2013)
『ワインの自由』 堀賢一著(集英社、1998)
『ワインの個性』 堀賢一著(ソフトバンククリエイティブ、2007)
『ブルゴーニュのグラン・クリュ』 レミントン・ノーマン著(白水社、2013)
Remington Norman, The Great Domaines of Burgundy 2nd Edition, Kyle Cathie, 1996
Clive Coates MW, Côte d‘Or, University of California Press, 1997
Anthony Hanson, Burgundy 2nd Edition, Faber & Faber, 1995
Allen Meadows, The Pearl of the Côte, BurghoundBooks, 2010
Jasper Morris, Inside Burgundy 2nd Edition, BB&R Press, 2021
Jancis Robinson , VTR Jancis Robinson’s Wine Course vol.2, 1994
Corie Brown, Henri Jayer, 84; Celebrated Producer of Burgundy Wines, Los Angeles Times, 2006
Per-Henrik Mansson, Not Quite Retired, Wine Spectator, 1997
Baghera/wines, Henri Jayer: the heritage, 2018
『賃借耕作と折半耕作』 堀賢一著
『クロ・パラントゥ: アンリ・ジャイエが蘇らせた畑』 堀賢一著









-300x200.jpg)