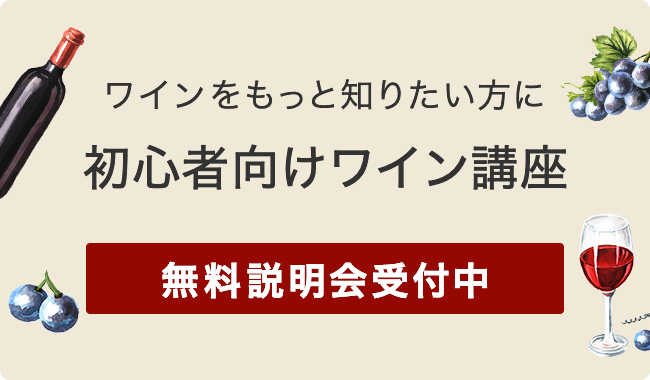「若いヴィニュロン達がヘマをしでかさないよう、私は手を貸したように思う。若い連中は、優れたワインを造るために必要な資金と技術の両方を持っている。奴らは、年かさのヴィニュロンと同じようにはしていない。つまり、くだらぬたわごとやら勘やらには頼ってないんだ。連中には好奇心がある。よく出かけるし、よくワインも飲む。だから、手前が能なしかどうか、わかるってワケさ。一昔前のヴィニュロンたちは他人と交わらなかったが、若い奴らはもっと話好きだ。良いモノができれば、ほかの皆の手本になる。秘密なんかない」
1990年代のアンリ・ジャイエが、ブルゴーニュワインの権威で著述家のレミントン・ノーマンに対し、語った言葉である。少しずつ手がける畑・ワインの量を減らし、引退に向かっていたこの時期のジャイエは、次世代にバトンを渡そうと、積極的に交流を図っていたのがうかがえる。その影響を受けた次世代の優良生産者たちは、師から何をどう受け継いだのか。どうあれ、2024年の今、コート・ドール産のピノ・ノワールは、歴史上最も高い品質水準に達しているように思われる。
5回シリーズで送る本記事、この最終回では、アンリ・ジャイエが現在に遺した正のレガシーとして、影響を受けた生産者たちについてを、負のレガシーとして、はびこる贋作問題を取上げる。「アンリ・ジャイエの現代性」と題するまとめのチャプターでは、この男の唱えた革新的なワイン造りが、現在のブルゴーニュでどう変容しているかを概観した上で、ロール・モデルとしてのアンリ・ジャイエを考察する。
【vol.5 目次】
7. アンリ・ジャイエの後継者たち
● エマニュエル・ルジェ
● ジャン・ニコラ・メオ
● その他の生産者たち
8. アンリ・ジャイエの贋作について
● ほとんど贋物!?
● 2018年 Baghera/Winesのオークション
● とりわけ難しいジャイエの真贋鑑定
9. まとめ:アンリ・ジャイエの現代性
● 耕作方法について(耕起、ビオディナミなど)
● 醸造法法について(全房発酵、亜硫酸量)
● ロール・モデルとしてのアンリ・ジャイエ
アンリ・ジャイエとは? ~世界で一番高価なワインを造った偶像破壊者
- Vol.1: 宝石より高価なワインに/アンリ・ジャイエの生涯
- Vol.2: アンリ・ジャイエのブドウ栽培
- Vol.3: アンリ・ジャイエのワイン醸造/ワイン熟成
- Vol.4: アンリ・ジャイエが所有・耕作していたブドウ畑
- Vol.5: アンリ・ジャイエの後継者たち/贋作について/まとめ
7. アンリ・ジャイエの後継者たち
エマニュエル・ルジェ

エマニュエル・ルジェ近影(写真提供:株式会社フィネス)
アンリ・ジャイエの甥で、段階的にジャイエ三兄弟のブドウ畑を受け継いでいったのが、エマニュエル・ルジェだ。パート1で述べたように、アンリが息を引き取る前年(2005)の収穫時期まで、ともにブドウ畑や仕込み場に立ち、指導・助言を受け続けた。直接的な後継者と言ってよく、そのワインの評価も極めて高い。アンリから、蔵の仕事を手伝うようにと、声がかかったのが1976年である。1985年からは、アンリの兄リュシアンのブドウ畑を折半耕作で借りてワインを造るようになり、その2年後には同じく兄ジョルジュの畑も借り始めた。1989年からは、クロ・パラントゥ、ボー・モンを含むいくつかの畑を、アンリから託され、元詰めを始めている。2005年以降は、長男のニコラが、2009年からは次男のギヨームも家業に加わった。
ワイン造りについては、耕作・醸造ともに、アンリ・ジャイエの造りほぼそのままである。茎の使用については、小規模に試してみた経験はあるものの、「除梗100%」の看板は変わっていない。新樽の割合については、クロ・パラントゥなど上級銘柄はアンリと同じ100%だが、村名格以下の比較的格下の畑については、ヴィンテージの性質などを考慮して、比率を上下させるようになった。
2018年、「叔父と過ごした特別な瞬間は?」と問うた、Baghera/Winesのインタヴュアーに対し、ルジェは次のように答えている。「1990年代の初め、仕込み作業の合間に、朝の軽食を取っていたときだよ。ブドウの収穫箱をふたつ、裏返して椅子代わりにして腰掛け、ふたりのあいだに置いたもうひとつの収穫箱をテーブルにしていた。つまんでいたのは、女房が作ってくれた鶏のテリーヌだった。叔父は、なにかを確認するつもりだったのか、一本のワインを抜いた。1959年のリシュブールだった……朝9時のオヤツに合わせてだよ!!とんでもない瞬間だったさ。ワインは途方もなかった。もちろん、私がそれまでに飲んだ中で、一番古いワインだった。これが、叔父のワインを飲んだ、最高の想い出だよ」
ジャン・ニコラ・メオ

ジャン・ニコラ・メオ近影(写真提供:株式会社フィネス)
ドメーヌ・メオ・カミュゼの現当主で、アンリ・ジャイエからワイン造りについて最初の手ほどきを受けたのが、ジャン・ニコラ・メオである。ジャイエは1988年までこのドメーヌから、リシュブールを含むいくつかの畑を折半耕作で借りていたのだが、それは当時の当主であったジャン・メオが、パリで政治家およびフランス国営石油研究所長としてのキャリアを優先した、不在地主であったからだ。ドメーヌの設立は20世紀のはじめ、同じく政治家のエティエンヌ・カミュゼによるが、元詰めが開始されたのは1984年からで、それまでは折半耕作契約で収められたワインもすべてネゴシアンに売られていた。ジャン・メオの息子、パリで経営学を学んだ若きジャン・ニコラ・メオが、このドメーヌに関わり始め、ジャイエに教えを請いつつワイン造りを始めたのが1985年、弱冠20歳のときだ。ジャイエの関与はそう長くはなく、1990年代初めには、すでにジャン・ニコラは独り立ちしていたというが、すぐさまトップ・プレイヤーたちの仲間入りを果たした。
ルジェと同じく、ワイン造りの流儀はアンリ・ジャイエのそれをほぼ踏襲しており、村名格以下のワインで新樽比率を調整するようになった以外は、大きな変更はない。今日大きなうねりになっている茎の使用についても、試験は行なってはいるものの、否定的な立場だ。2020年に筆者が行なったインタヴューで、茎の使用について次のように答えている。
「全房での仕込みも試してはみたのだが、私の好みではなかった。アンリ・ジャイエに育てられたし、最初からアンリが教えてくれたワインのスタイルが好きだったんだ。ちがうふうにしようとは考えなかった。師のやり方が好きだったし、師のワインが好きで、師の教えで造った自分のワインが好きだった。なので、全房発酵にはまったくそそられるところはなかったんだが、それでも試してはみた。だから、その良し悪しについて語れるんだ。40、60、80、100%と、いろんな比率で全房を試したが、どれも気に入らなかった。全房でできるワインが好きな人はいて、そういう人にとってはよいワインなのだろうが、自分の好みでなければ意味がない。私の味覚は師であるアンリ・ジャイエと同じで、フレッシュで、活き活きとしていて、みずみずしい酸や果実味が連想されるアロマをもち、除梗で生まれる豊潤で滑らかな口当たりを好むのだ。全房発酵で造ったワインが、悪いワインだとは言わない。単に私の好みではないというだけでね」
その他の生産者たち
一線を退いたあとも、コート・ドール中から多くの造り手たち、とりわけ若い世代がジャイエのもとに足を運び、教えを仰いだのはよく知られている。皆、自分が仕込んだワインを持参し、ジャイエは喜んで味見をし、感想を述べ、時には手厳しい技術的な指摘をした。数があまりに多いため、そうした生産者の名をすべて、ここで紹介するのは叶わない。ジャイエの友人であった著述家のジャッキー・リゴーが1997年に上梓したインタヴュー本、『Ode aux grands vins de Bourgogne: Henri Jayer, vigneron à Vosne-Romanée』(邦訳『ヴォーヌ・ロマネの伝説 アンリ・ジャイエのワイン造り』)に、ジャイエを称賛するコメントを寄せた造り手たちは、以下のような面々である。蒼々たる顔ぶれだ。
- アンヌ・グロ
(ドメーヌ・アンヌ・グロ Domaine Anne Gros / ヴォーヌ・ロマネ) - ドミニク・ラフォン
(ドメーヌ・コント・ラフォン Domaine Comtes Lafon / ムルソー) - ブリュノ・クレール
(ドメーヌ・ブリュノ・クレール Domaine Bruno Clair / マルサネ) - ドニ・モルテ
(ドメーヌ・ドニ・モルテ Domaine Denis Mortet / ジュヴレ・シャンベルタン) - アラン・ビュルゲ
(ドメーヌ・アラン・ビュルゲ Domaine Alain Burguet / ジュヴレ・シャンベルタン) - フランソワ・フェヴレイ
(ドメーヌ&メゾン・フェヴレイ Domaine & Maison Faiveley / ニュイ・サン・ジョルジュ) - フィリップ・シャルロパン
(ドメーヌ・フィリップ・シャルロパン Domaine Philippe Charlopin / ジュヴレ・シャンベルタン)
2000年にジュヴレ・シャンベルタンで、マイクロ・ネゴシアンの「ルー・デュモン Lou Dumond」を起ち上げた日本人醸造家の仲田晃司氏も、晩年のジャイエと親交があった。「自分自身のアイデンティティをワインに表現せよ」との薫陶を、翁から受けたという。海外では、カリフォルニア州サンタ・バーバラ郡におけるブルゴーニュ品種のパイオニア、オー・ボン・クリマ Au Bon Climatの故ジム・クレンデネン(2021年逝去)が、ジャイエを師と仰ぎ、深いつながりがあったと広く知られている。
8. アンリ・ジャイエの贋作について
ほとんど贋物!?
アンリ・ジャイエのワインは、御大が完全引退をした2001年から20年以上が過ぎた今も、二次流通市場で取引されている。値段はパート1で紹介したようにべらぼうで、これからも上がり続けそうに思われる。しかしながら、意外にも市中在庫は潤沢だ。クリスティーズ、サザビーズといった一流オークションハウスの競りだけでなく、一般的なネットオークションでも普通に売り買いされている。国内最大手の某ネットオークションを今のぞいてみたところ、10点近くの出品があった。ジャイエのワインは高価だが、金さえ出せば今でも簡単に手に入るのか? 答えはノーだ。
そもそも、アンリ・ジャイエは一年に何本のワインを生産していたのか。ヴィンテージによる山谷があるのに加え、メオ・カミュゼや他の兄弟、親族との間で畑を借りた・返したのやりとりが猛烈に複雑なため、正確な推定は困難を極める。一番多かった時期で、約5ヘクタールの畑を耕していたようだから、平均収量を35ヘクトリットルと仮定して、年産1500ケース(1.8万本)ほど。メオ・カミュゼにリシュブールなどの畑を返した1980年代末から1995年までは、650ケース(7800本)程度仕込んでいたと言われる。最終フェーズの1996年から2001年までは、クロ・パラントゥを0.28ヘクタールだけだから、75ケース(900本)程度という極少量しかない※。現代の消費動向下では、どんな高級ワインであれ生産から10年以内に9割以上が消費されるのが常。こんなに小さな生産規模のワインたちが、開封されずに市場にたくさん残っているのは、明らかな異常でしかない。
※ ただし、この時期にも、いわゆる「ジョルジュもののアンリ・ジャイエ」のエシェゾーおよび村名格ニュイ・サン・ジョルジュが、わずかな量だけ生産されていた。これらについては正確な耕作面積がわからないので、生産本数も不明だが、せいぜい1樽か2樽(300、600本)、あるいはそれ以下だったと想像される。「ジョルジュもののアンリ・ジャイエ」とは、アンリが兄ジョルジュの所有畑を折半耕作契約で借りて、生産・瓶詰めしていたワインのことだ。一見するとそのラベルは、アンリ自身のワインと同じようだが、ラベル上部中央の家紋がアンリのものとは異なっているのに加え、ラベル最下部には小さな文字で、「GEORGES JAYER PROPRIÉTAIRE A VOSNE-ROMANÉE – FRANCE」と横書きされている。この横書き文字の真上には、比較的大きな文字で「Henri Jayer」と書かれているのだが、すぐ上には非常な小さな文字で、「Élevé et Vinifié par」(~によって醸造・熟成された)との記載がある。ジャイエ自身の持ち分である畑の場合、この「Élevé et Vinifié par」の位置には、「Mise un bouteille par」(~によって元詰めされた)の文字が置かれているのが違う。
答えはひとつ、「現存するアンリ・ジャイエのほとんどは贋作」という、悲しい事実推定だ。高級ワインを偽造する犯罪は、ワインの歴史と同じぐらいに古いのだが、その市場価格が高騰を始めた20世紀末から、贋作ボトルは世界規模で急増した。世間の耳目を引いたのは、2014年にFBIによってアメリカで逮捕された、インドネシア人の偽造王 ルディ・クルニアワンの事件である(懲役10年の刑に処されて服役し、2021年に出所)。クルニアワンの手による贋作の本数は、正確にはわかっていないのだが、相当量が高級ブルゴーニュで、その中には当然ジャイエの銘柄も含まれていた。ルディがオークションを通じて世界に放った偽造ブルゴーニュは、ババ抜きのジョーカーよろしく、今も各地で売買され続けていて、その量を推定するのは難しいが、100本や200本といった可愛いオーダーではないようだ。そしてもちろん、ジャイエの偽造はなにもルディの専売特許ではない。個人が自宅でDIY的にこしらえる稚拙な代物から、組織犯罪者たちが相応のノウハウに基づき仕上げる精巧な「そっくりさん」まで、今この瞬間もジャイエの贋作は、せっせと作られているだろう。

米連邦当局が押収したルディの贋作ワインは、クレーンで破壊された。各ボトルのラベルに、「COUNTERFEIT」のスタンプが押されているのが見える ©Lynzey Donahue – US Marshals
2018年 Baghera/Winesのオークション
そんな状況下、数多のブルゴーニュ・コレクターたちが、顎を落とすほど驚く事件が起きる。2018年6月に、スイスの新進オークションハウスであるBaghera/Winesが行なった、大がかりなアンリ・ジャイエのオークションである。アンリのふたりの娘、リディエとドミニクが、父のセラーにあったライブラリー・ストックを一挙に放出したという触れ込みで、その数なんと1000本以上(レギュラーボトル 855本、マグナムボトル 209本)。出品されたヴィンテージは、1970から2001年までにわたっていた。最高落札ロットは、1978年から2001年までの15ヴィンテージが含まれる、クロ・パラントゥのマグナム瓶のセットで、驚天動地の116万スイスフラン(当時の為替で約1.3億円)。オークションの総落札額は、3450万スイスフラン(約39億円)という莫大な値であった。
このオークションについては、開催が告知された時点から、その真正性を疑う声がいくつも上がっていた。ルディ・クルニアワン逮捕にも協力した高級ワイン真贋鑑定の第一人者、米国のモーリン・ダウニーは、「都合がよすぎる(too good to be true)」と否定的なコメントをしたし、サザビーズやクリスティーズをさしおいて、設立から3年しか経っていないスイスの新参ハウスにこれほどのお宝が委ねられた経緯についても、さまざまな噂が出た(「英国の二大ハウスは、真正性が担保されないとして、出品を断った」など)。しかしながら、Baghera/Winesが発行したオークションカタログには、甥のエマニュエル・ルジェ、DRCの当主(当時)であったオベール・ド・ヴィレーヌといった人物が言葉を寄せているし、近しい身内しかアクセスしえないであろう、ジャイエの持ち物、道具、写真などが多く掲載されているのを目にすると、すべて蔵出しの由緒正しきボトルたちと考えるのが妥当であろう。本物が枯渇し、贋物ばかりになっていた市場に、1000本もの折り紙付きが新しく供給されたわけだ。このオークションで落札されたブツが今、収集家のセラーの奥にしまい込まれているのか、利ざやを稼ぐためにすぐに転売に回されているのか、あるいは幸運な飲み手のノドを通っているのかは、筆者にはわからない。
なお、このオークションに出品されたワインはすべて、2018年2月に新しいキャップシールが施され、新しく刷られたラベルが貼られた。リコルク、リフィルはなされていない。
とりわけ難しいジャイエの真贋鑑定
21世紀に入って以降、贋作家のターゲットになりやすい世界の高級ワイナリーは、遅まきながら対策を始めた。ボトルにエンボスを入れる、ラベルやキャップシール上の文字を毎年微妙に変えるといったアナログな手法から、不可視インク、ホログラム、すかしといった紙幣にも使われる特殊印刷技術のラベルへの利用まで、守るべき名声を背負うワイナリーは、手を変え品を変え努力を重ねている。2007年に登場し、急速に普及しているプルーフタグ(Prooftag)も、なかなかに強力なツールだ。これはQRコードを使い、インターネット経由で真正品かの確認ができる仕組みの特殊な封印シールで、瓶口上面からキャップシールへ、その裾から瓶首ガラス面最上部をまたぐようにボトルに貼られる。「本物の空き瓶を再利用して、贋のワインを詰める」という手口にも対応できるのだが、このプルーフタグ自体が、やや剥がれやすいという欠点があるとされる(剥がされたタグ自体は、一部のデザインが変わったり、「VOID」の文字が浮かび上がったりするように設計されているため、別のボトルに再度貼り付けての利用はできないものの、オリジナルのボトルから取り除けはする)。このほか、ブロックチェーン技術を利用して、ワインのトレーサビリティを保証しようという試みは始まっているが、いまだ普及可能な段階には至っていない。真贋鑑定については、ハイテク光学技術を用いて、瓶の外側から中身が本物かを確かめようとするいくつかの技術が研究途上にあるが、こちらもまだ頼りに出来るだけの精度に達してはいないようだ。
さて、話はアンリ・ジャイエである。彼のワインに施されている偽造対策は……あろうことか、ほぼゼロであった。どのワインのコルクにも、特定のパターンで焼き印が入っている点を除き、なんのプロテクションもなされていない。ジャイエが現役の頃には、上述の贋作防止テクノロジーの多くは存在していなかったし、そもそも本人に「贋物が出回るかも」という危機感がなかったのだろう。当時のブルゴーニュワインは、DRCを除けばどのドメーヌもジャイエと同じような状況だったので仕方がないのだが、この無防備が今日の悪夢につながっている。
もちろん、高級ワインの真贋鑑定を生業とする専門家は、ジャイエの見極めもできる。ラベルの文字列、フォントの種類と文字の大きさ、紙の質、印刷方法、利用インク、紙の汚れや劣化具合、ボトルのエンボスや色、キャップシールの材質や色、瓶底の澱の質、コルクの刻印、液面の高さなどなどを、時には専用の器具を使って吟味し、総合的に真贋に関する見解を出すのだ。ただ、ことジャイエに関する限り、「100%本物である」と保証するのは難しいという(逆に、「100%贋物である」と断言するのは、容易な場合が多い)。これは、真贋鑑定に必要な諸要素にまつわる情報を、照会する相手が墓の中だからだ。一例をあげれば、ジャイエはその長いキャリアのある時期に、キャップシールの材質をAからBへと変更した。移行は数年にわたっている模様なのだが、その過渡期において、どの銘柄にどちらの材質のキャップシールが用いられたか、記録が残っていない。一代で終わってしまった個人ドメーヌの痛いところだ。
不思議なのは、ジャイエの贋作には、あまり人気のない平凡なヴィンテージ(たとえば1986、1987、1991)や、格下アペラシオン(たとえばブルゴーニュ・パストゥーグラン)の銘柄が、少なからず見られる状況だ。我々素人は、「同じ手間暇をかけて造るなら、偉大なヴィンテージの特級畑か一級畑のワインを」と、贋作家の心理を想像しがちだが、こうした予断を逆手に取っているらしい。要するに、アンリ・ジャイエとラベルに謳われたボトルは、どんな顔をしていても贋作の可能性が高い、という悲しい結末になる。
それでもまだ、入手できる本物の数はゼロではないだろう。大枚をはたいてでもジャイエを飲みたいと思うなら、最大限信頼できるルートから買うしか道はない。100%はないから、ある程度は賭けだ(そもそも、古酒そのものが博打のようなもので、本物でも熟成のピークを過ぎていたり、状態に問題があったりというハズレはいくらでもある)。何をもって信頼できるとするかは、いくつか考え方があろう。たとえば、1980年代(あるいはそれ以前)から継続的に蒐集してきた個人コレクターの所蔵品なら、真正品である可能性が高そうだ。ジャイエが現役だった時分に購入されたのなら、贋作がまだほとんど出回っていなかったからである。ただ、そのコレクター氏が嘘つきなら話は別なので、専門家の目が通ったボトルのほうが、信頼度が高いと考えられもする。信用に足るオークションハウスが扱うアイテムは、プロの鑑定家が真贋を見極めて合格した品のみが出品されるから、安心度は上がる。国内であれば、日本随一のワイン鑑定家でもあるワイン研究家、堀賢一氏が現在鑑定人を務めているオークションハウス、「Top Lot」がお勧めだ。このハウスの出品物であれば、ジャイエであれ何であれ、同氏の目を通っている。なお、堀氏はジャイエの鑑定にあたっては、必ずキャップシールを切り、瓶口にささったコルクを確認するという。このプロセスを抜きにしては、精度が十分に高くないと考えるからだというが、ここからもジャイエの真贋鑑定の難しさがうかがえる。
蛇足ながら、何のフィルターも通さずに、見えない相手と取引をする一般のネットオークションは、ジャイエに限らず贋作ワインの温床である。したがって、「フェイク・ボトルを一度見てみたい」という動機以外では、利用をお勧めしない。
9. まとめ:アンリ・ジャイエの現代性
耕作方法について(耕起、ビオディナミなど)
「ブルゴーニュのワイン造りのヴィジョンを変えたのは私なんだ」と、2004年のアンリ・ジャイエは述べた。たしかにそうだ。ただ、そこから20年が過ぎ、ブルゴーニュは変わり続けてきた。新しい風を導き入れた造り手たちの中には、ジャイエから薫陶を受けた弟子も少なからず含まれている。ここからは、ジャイエからバトンを受け取った次世代の生産者たちが、何をどう変えたのか、いくつかのポイントに絞って簡単に見ていきたい。まずはブドウ畑での仕事からだ。

ヴォーヌ・ロマネ村に植わるピノ・ノワールのつぼみ。まもなく花が咲く
ジャイエは、土を耕すのを重視した。ヴィニュロンを怠け者にした、化学合成除草剤を使うのではなく、鋤を土に入れる。土壌に空気を含ませ、ほぐす。雑草を土にすき込んで肥料にし、地表近くに伸びているブドウ樹の根を切る。除草剤が撒かれたカチカチの死んだ土に対して、鋤の入ったフカフカの土は、生きていると称賛された。しかし今日では、そこから一周して、「耕さない」ムーヴメントが起きている。土を耕すと、その構造が壊れてしまうだけでなく、蒸発による水分ロスを促進してしまうから、というのがその理論的背景で、暑く乾燥した生育期間が昔より増えたのに対応した動きだという。秋の収穫後に畝間にカヴァー・クロップ(被覆植物)を植え、春になると刈り込んで畝間を覆うマルチにし、ブドウ樹から水を奪わずに、生育期間中の雑草繁殖を抑えるという手法である。後述の除梗比率の技術選択と同じく、気候変動がこの変化の背景にはある。
ビオディナミの普及・隆盛も、この20年間の特筆事項であろう。ルフレーヴ、ルロワといった先駆者たちは、1990年代の初めにはこの農法を取り入れていたから、ジャイエも当然意識はしていた。2004年時点での翁の評価は、どちらかというと否定的。この年のインタヴューでは、ルロワが1993年に防カビ剤を使わなかったために、ベト病で畑がほぼ全滅したエピソードをジャイエは挙げ、リュット・レゾネで十分ではないかとコメントしている。それから20年。この農法に取り組む者たちがよく口にする、「ビオディナミを続けるうちに、ブドウ樹が病気に強くなる」効果のせいか、はたまたビオディナミに適した樹冠管理や防除技術のノウハウ蓄積のおかげか、昨今は「ルロワの悲劇」のような話は聞かなくなった。実践者は、着実に増え続けている。とはいえ、まだまだこの農法のもつオカルト的な側面に違和感を覚え、距離を取る生産者はブルゴーニュでも少なくはない。
ここ5年ほどでは、フィトセラピー(植物療法)と呼ばれる、ブドウでは新しい栽培技術も、コート・ドールで広まりつつある。草花、葉、樹皮などを煎じた茶のような液体を作り、畑に散布すると、植物の種類によって防カビ作用があったり、樹の生育を促進する肥料のような役割を果たしたりするようだ。こちらは、ジャイエにとって初耳のテクニックだろうが、翁はどんなふうに見ただろうか。
醸造法法について(全房発酵、亜硫酸量)
除梗比率については、完全にフェーズが変わった。今のコート・ドールは、右を見ても左を見ても、全房発酵ばかり。もちろん、ルジェやメオのように、師の教えを固く守り続ける造り手はいるが、完全除梗派はもはやマイノリティに転じた。全房発酵100%の造り手と完全除梗派の間には、一部は全房、一部は除梗と仕込むタンクによって使い分ける者、除梗した果粒と全房をラザニアのように同じタンク内で重ねる者、除梗をしたあと茎の一部をタンクに投入して戻す者などなど、考えつく限りのバリエーションが存在する。いずれにせよ、アンリ・ジャイエが「ワインに不要」と切って棄てた茎が、コート・ドールに戻ってきた。なぜなのか。
全房発酵のメカニズムについて、ここで詳述はしないが、果梗=茎を使う主要なメリット、デメリットは次のように整理される。メリットのひとつめが、ピノ・ノワールには不足しがちなタンニンを、茎から得られる点。骨格のあるワインが造りやすくなる。ただし、茎が完熟して十分に木質化していなければ、これはデメリットに変わる。粗い未熟なタンニンが、青臭い風味とともにワインに移ってきてしまうのだ。茎を使うと、酸味が少し落ちてしまうのは、デメリットだろう。しかしながら、酸味が下がりながらも、ワイン全体の風味のフレッシュさは増す、というのは全房発酵の実践者が口を揃えて唱えるメリットだ。アルコールは、若干下がる。これは、温暖化によるアルコール過剰がブルゴーニュですら問題になってきた今、メリットに振り分けられるだろう。茎は黒ブドウの色素を吸収してしまうため、ワインの色は少し薄くなるが、これはメリットでもデメリットでもない。色が濃い赤ワインのほうが、評論家などから高い評価を得やすいのは事実だが、もともと果皮に色素の少ない性質のピノ・ノワールは例外で、さほど色の濃淡は問題にならない(また、全房でもDRCやルロワのように、色の濃いピノは存在する)。
ブルゴーニュワインの権威で著述家のジャスパー・モリスは、この全房発酵の流行について、主に理由はふたつだと述べた。ひとつは、2006年にアンリ・ジャイエが逝去し、弟子たちの「遠慮」がなくなった点。もうひとつは、気候変動による地球温暖化によって、茎が以前よりも完熟するようになった点である。ジャイエが忌み嫌った「青臭い茎」が、環境の変化で見られなくなったのだ。実際、ヨーロッパ中が酷暑に見舞われた2003年について、甥のルジェのセラーで仕込みを手伝っていたジャイエは、「9月まで収穫を待てば、果梗が完全に熟していたので、取り除く必要がなかった」と述べており、除梗派の教祖本人が、必ずしも教条主義的ではなかったという意外な事実を露呈させている。かつて、カリウム肥料漬けになっていたブルゴーニュの畑が、自然なブドウ栽培に舵を切り直してから、それなりの歳月が経過した点も、全房発酵の復帰・普及には有利に働いた。土壌中のカリウムが徐々に減ったので、果梗に含まれるカリウム量も減り、ワイン中の酸と結びついて酸を押し下げる程度がさほど問題ではなくなったのだ。
亜硫酸添加量の減少(あるいは無添加)も、ジャイエ逝去後の目立った潮流だ。ジャイエ自身、当時の標準からするとかなり少ない添加量ですませていたのだが(破砕時に50ppm、瓶詰め時に13ppm)、今日のブルゴーニュではその半量程度しか加えない造り手が珍しくなくなった。タイミングについても、全房発酵で仕込む生産者の中には、亜硫酸が茎から青臭い風味を抽出するからと言って、搾るまで添加しない、あるいは瓶詰め直前まで添加しない者もいる。まだまだマイノリティだが、全工程で一切添加しないまま、瓶詰めする強者だっているのだ。
ジャイエは晩年のインタヴューで、亜硫酸は少量であっても必要で、自身のワインはそのおかげもあって、「25年から40年はもつ」のだと長寿ぶりを誇っていた。たしかに事実である。一方、亜硫酸無添加ワインについては否定的で、2~3年の寿命しかもたないと腐したのだが、こちらはどうか。無添加ワインでも、20年以上美しく熟成する「反証」が、ブルゴーニュでも見られ始めている。そんなボトルをジャイエに飲んでもらい、意見を聞きたいものだ。
ロール・モデルとしてのアンリ・ジャイエ
「どの時代にもそれぞれの問題があり、そのたびに変化に従わなければならない」と、晩年のアンリ・ジャイエは述べた。ジャイエが生きた時代のブルゴーニュは、化学肥料と殺虫剤、除草剤で損なわれた土壌、ピノ・ノワールが容易には完熟しない気候があり、セラーでは古くからの非合理な因習が幅を効かし、どうにかまともに熟成まで終えられた数少ないワインも、瓶詰めトラックの激しい濾過によって台無しにされていた。そもそも、数ヘクタールの畑しか持たない小農家は、一部の名門を除いてワインの元詰めはせず、ブドウのままか、あるいは発酵の終わったワインを樽に入れて、大手のネゴシアンに売るのが普通だった。
1994年、BBCのテレビシリーズ撮影のために、雨がそぼ降るヴォーヌ・ロマネの畑に立ったジャンシス・ロビンソンは、カメラに向かいこんなふうに述べている。「まともなブドウが実ったと言える年はせいぜい3年に1度しかなく、ロクでもないワイン造りがしばしばなのに、引き合いだけがやたらと多い。私が思うに、ブルゴーニュの赤ワインが5本あれば、4本はがっかりする味わいだ」。こんな悲惨な状況を変え、今日燦然と輝くコート・ドールへの道筋をつけたのが、アンリ・ジャイエであった。周囲からは、「夢想家、ユートピア主義者だと見られていた」のだと本人は言うが、くじけなかった。

セラーに向かうアンリ・ジャイエ。その「背中」はあまりにも大きい
弟子のドミニク・ラフォンは、こんなふうにジャイエを評している。「ぼくにとっては、アンリ・ジャイエは技術というより、ひとつの思想だね。物の見方とか、気質が面白いんだ。もちろん、ブルゴーニュワインについて考えるとき、アンリは避けて通れないが、大事なのは結果よりも方法論なんだよ」。ワイン造りの名人アンリ・ジャイエが、若い世代に伝えたかった物事の核心は、技術そのものではなかったのではないか。変化に対処し、新しい道を切り開いていくマインドセットこそが肝要だと、自分の背中を見せていたように思われてならない。「流行に左右されるな」、「自分が美味しいと思うワインを造れ」といった諫めも、ジャイエが若い世代に遺した言葉である。
数年前、30歳を少しばかり超えた年齢の、ブルゴーニュの醸造家と話していたときのこと。筆者は、「アンリ・ジャイエのような古典的な造り」という、相手の言葉に軽い衝撃を受けた。時代は着実に進んでいる。今の若きブルギニオンにとって、アンリ・ジャイエはすでに「ラディカル」ではなく、「クラシック」なのだ。まあしかし、それはたいした問題ではない。この先、フィトセラピーが常識になろうとも、除梗が忘れ去られた技術になろうとも、「アンリ・ジャイエ的なもの」の重要性が失われはしない。ジャイエが遺したワインは、いずれ飲み尽くされて無くなるだろうが、その名は残る。ドミニク・ラフォン言うところの「思想としてのアンリ・ジャイエ」は、自己超克のロール・モデルだ。それはこの先も長く長く、コート・ドールの地で生き続けるに違いない。
【主要参考文献】
『ヴォーヌ・ロマネの伝説――アンリ・ジャイエのワイン造り』 ジャッキー・リゴー著(白水社、2005)
『アンリ・ジャイエのブドウ畑』 ジャッキー・リゴー著(白水社、2012)
『ほんとうのワイン――自然なワイン造り再発見』 パトリック・マシューズ著(白水社、2004)
『最高のワインを買い付ける』 カーミット・リンチ著(白水社、2013)
『ワインの自由』 堀賢一著(集英社、1998)
『ワインの個性』 堀賢一著(ソフトバンククリエイティブ、2007)
『ブルゴーニュのグラン・クリュ』 レミントン・ノーマン著(白水社、2013)
Remington Norman, The Great Domaines of Burgundy 2nd Edition, Kyle Cathie, 1996
Clive Coates MW, Côte d‘Or, University of California Press, 1997
Anthony Hanson, Burgundy 2nd Edition, Faber & Faber, 1995
Allen Meadows, The Pearl of the Côte, BurghoundBooks, 2010
Jasper Morris, Inside Burgundy 2nd Edition, BB&R Press, 2021
Jancis Robinson , VTR Jancis Robinson’s Wine Course vol.2, 1994
Corie Brown, Henri Jayer, 84; Celebrated Producer of Burgundy Wines, Los Angeles Times, 2006
Per-Henrik Mansson, Not Quite Retired, Wine Spectator, 1997
Baghera/wines, Henri Jayer: the heritage, 2018
『賃借耕作と折半耕作』 堀賢一著
『クロ・パラントゥ: アンリ・ジャイエが蘇らせた畑』 堀賢一著