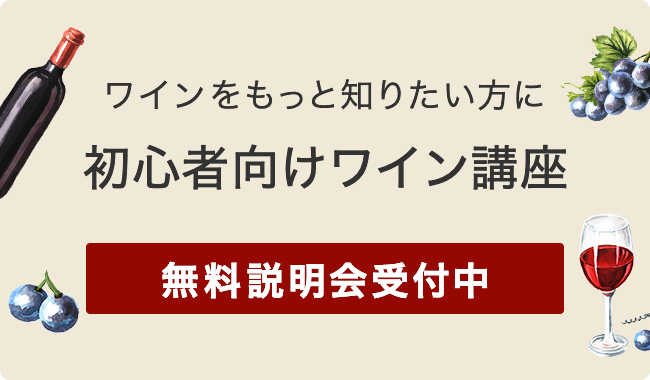コート・ロティのシラーを嗜む機会は、愛好家の方には比較的あることでしょう。でも、エルミタージュを楽しむことは、少ないのでは無いでしょうか?その昔は、北ローヌの名実共に最高の産地。今では、コート・ロティの復活と再興を横目に、一般受けよりも、このワインを愛する玄人から安定した人気を誇っています。
【目次】
1. エルミタージュ、最高のシラーが生まれる土地
2. ボルドーを支えたエルミタージュの赤
3. シラーのグローバル化の要となったエルミタージュ
4. 憶えておきたいエルミタージュの代表的な区画
5. 高級赤ワインと白ワインが両立する産地
6. 大手生産者たちの牙城
7. 試してみたいエルミタージュの優良ヴィンテージ
8. エルミタージュのまとめ
1. エルミタージュ、最高のシラーが生まれる土地
エルミタージュは、北部のコート・ロティから60キロメートルほど南下した北緯45度に立地。温和な大陸性気候で、夏場でも平均気温は21度程度。年間2800時間の日照時間に恵まれています。降雨量は年間1000ミリ弱ありますが、秋と春に纏まっています。
アペラシオンの面積は、コート・ロティと比べても半分以下。約140 ヘクタールしかありません。ちなみに、メドック格付け第1級のシャトー・ラフィットは110ヘクタール。ボルドーのシャトーひとつ分の栽培面積ほどしか無いアペラシオンなのです。
希少性も高く、赤ワインは1万円以下のワインを探すのが少々難しいほどです。コート・ロティには高いワインも多くありますが、1万円を割るワインも多く、一般愛好家でも手が届きます。
混同してはいけないのは、クローズ・エルミタージュ。こちらは、エルミタージュの北と南に広がる1,500ヘクタールにも及ぶ広大な産地で、別のアペラシオンです。
北ローヌでは最も歴史と伝統に恵まれた産地。タン・レルミタージュの町の背後に立ち上がる急峻な南向きの急斜面。太陽を存分に浴びて、風から守られた土地が、香り高く骨格がしっかりした、長期熟成が可能なワインを生みます。
エルミタージュでは、ローヌ川が北から南へと流れます。その左岸、つまり東側がエルミタージュ。そして、川が西から東への流れに向きを変えるところに、南向きの斜面が立地しています。

南から北へと流れるライン川が東から西への流れに向きを変える、ドイツの銘醸地ラインガウを、どこか思い起こさせます。
エルミタージュの土壌で、高品質のシラーを生むのに花崗岩は欠かせません。クローズ・エルミタージュの一部の産地でも、この母岩が伸びているので良いワインが産出すると言われます。その母岩の上には、500万年前の第3紀鮮新世から、現在に至る第4紀という若い地質時代の粘土質などの堆積物が土壌を構成しています。
アペラシオンの西側には、花崗岩が多いシラーの銘醸畑が集中。一方、東側の区画は、アルプスの影響を受け、砂質や粘土質やレス土壌(黄土)が混在します。最高でも200メートルに届かない低標高の区画には、マルサンヌなどの白ブドウの栽培が多く見られます。
2. ボルドーを支えたエルミタージュの赤
エルミタージュは、ローマ時代から知られた土地で、『博物誌』で知られるプリニウスにも祝福された産地。
このアペラシオンの有名な伝説は、中世のアルビジョア十字軍の遠征の時代にさかのぼります。1224年に、ブランシュ・ド・カスティーユの騎士であったガスパール・ド・ステランベール。遠征に疲れ果てこの地で、隠居したと伝えられます。そして、祈りとブドウ栽培に身を捧げ、隠修士という意味合いを持つこのエルミタージュという地名になったといいます。少なくとも、16世紀には複数の隠修士がこの地に住んでいたというのは事実のようです。

サン・クリストフ礼拝堂。ガスパール・ド・ステランベールが建設したとされる
17世紀のフランス、ルイ13世の宮廷でもエルミタージュは振舞われました。1787年にはフランス大使時代の、後のアメリカ大統領トーマス・ジェファーソンも訪問しワインを購入。
エルミタージュの赤ワインは、ボルドーのネゴシアンに販売され、19世紀には大半がボルドーに送られるようになります。ボルドーのワインにブレンド。19世紀半ばにはボルドーやブルゴーニュの高級ワインと同等の価格で取引されるまでになりました。
ワイン批評家の先駆けと言えるアンドレ・ジュリアンが世界の銘醸地の中で、シャトー・ラフィット、ロマネ・コンティと肩を並べる存在として、エルミタージュを取り上げました。
ボルドーの格付け3級のシャトー・パルメ。シラーをブレンドしたワインを、「ヒストリカル19世紀ブレンド」と名づけて、発表。19世紀にボルドーワインが、ローヌのシラーをブレンドしたことへのオマージュというわけです。
3. シラーのグローバル化の要となったエルミタージュ

19世紀には、シラーは、エルミタージュではプティット・シラーと呼ばれ、ローヌ川を挟んで対岸のコート・ロティではセリーヌと呼ばれていました。
クローン違いであるとか、結局はシラーのシノニム(別名)に過ぎないなど様々な説がありますが、異なった個性を持つと考えられていました。
エレガントなコート・ロティと比べて、エルミタージュは力強く、黒胡椒のトーンは控えめ。色合いは濃くて、タンニンがしっかりしたワインになります。色も薄くタンニンも弱かった、昔のボルドーのブレンド相手として、重宝されていたのも頷けます。
近年は、温暖化の影響も有って、黒プラムを含めた、熟度が高い果実を感じるワインが早い内から楽しめるようになっています。
オーストラリアのシラーズ。ジェームズ・バスビーが、エルミタージュから挿し木を持ち込んだ歴史があります。先ずは、ハンター・ヴァレーで広く栽培されるようになります。1860年代にはシラーズ或いはエルミタージュとして知られるようになりました。
かの有名な、ペンフォールズのグランジ。このワインは、1989年まではこのエルミタージュの名前を冠していました(英語読みでハーミテージと発音します)。
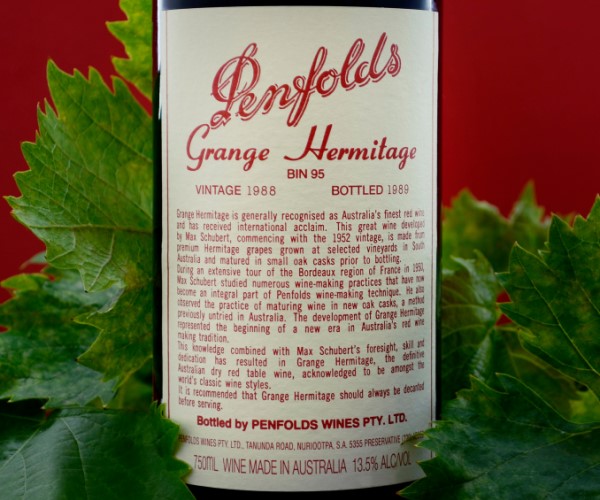
by millefloreimages – stock.adobe.com
ニュージーランドでは、長い間見向きもされなかったのですが、ストーンクロフト・ヴィンヤーズの創業者であるアラン・リマ―博士が光を当てました。以来、リマ―・クローンともエルミタージュのマーサル・セレクションとも呼ばれて、ホークス・ベイで広く活用されています。
4. 憶えておきたいエルミタージュの代表的な区画
20ほどのエルミタージュの区画の中でも、レ・ベサール、ル・メアル、レルミット、ボーム、レ・グレフューが代表的な区画。
レ・ベサールは、花崗岩土壌が支配的で、南向きの斜面にも恵まれています。エルミタージュの中核的な区画。もっともタンニンが豊富で凝縮度も高い長期熟成可能なワインを生みます。
東側に隣接するル・メアルも、南向き斜面。小石が多くてレ・ベサールよりも暖かい生育環境。ボディは厚めで果実感が豊かになります。
ですから寒くて果実が熟し難い年には、レ・ベサールに、ル・メアルをブレンドする事で熟度が高いワインになりますし、暑い年でも、レ・ベサールがブレンドされる事でしっかりした骨格が得られるわけです。
レルミットとボームは標高が高いので、軽くてアロマティックなワインができると言われます。レ・グレフューは、斜面の下部の麓。花崗岩の土壌もありますが、粘土質や石灰岩の土壌が混在します。
ブレンドか単一区画か
このレルミットにある、サン・クリストフ礼拝堂、ラ・シャペルが、ド・ステランベールが13世紀に生活をした地と言われています。
ポール・ジャブレのトップ・キュヴェ、ラ・シャペルは、この地の名称に因んでいます。でも、実際はレ・ベサール、ル・メアル、レ・グレフューなどのブレンドです。ポール・ジャブレやジャン・ルイ・シャーヴを始めとして異なる小区画のワインをブレンドするのが一般的です。
小規模生産者を除けば、シャプティエやドゥラス・フレールなどが単一区画にこだわっている他は、単一区画のみからワインを造る生産者は少数派です。
シャプティエは、区画をブレンドしたキュヴェをHermitage、単一区画のキュヴェをErmitageとラベルに記載して区別。エルミタージュの綴りは、一般的にはHermitageと’H’から始まりますが、シャプティエは、英国人が発音しやすいように、’H’が付くようになったと解説しています。
5. 高級赤ワインと白ワインが両立する産地
コート・ロティ程は急峻ではありませんが、エルミタージュでも350メートルの標高があります。ですから、土壌の浸食や流出を手直ししなければなりません。一方で、南向きの急斜面は、北風のミストラルからブドウを守り、十分な日照を受けた素晴らしいワインを生み出します。
エルミタージュの斜面では、低い樹高の株仕立てで支柱1本に新梢を結び付けます。平たんな土地では短梢剪定の垣根仕立てが一般的。斜面のヘクタール当たり1万本から、平坦な畑でも7,500本ほどの高い植栽密度が採用されています。古木も多く、収量が低い産地です。
赤ワインの全房発酵は流行のひとつとして、昨今、良く話題に上がります。全房のメリットとして、香りの複雑味や若干アルコールも低くなり、フレッシュ感がでることなどを挙げる生産者は多いです。
でも、1800年代の除梗機が発明される以前から、エルミタージュでは、人手を掛けて除梗をしていました。特にブドウの成熟度が低い年なら尚更のこと。今でも、ジャン・ルイ・シャーヴ他、多くの生産者は除梗します。
一般的には、発酵はステンレスタンク、熟成には新樽使用は控えめになって、大きな木桶や600リットル程度のドゥミ・ミュイが使用されることが多い様です。
混醸は北ローヌで伝統的な醸造方法。コート・ロティなら、シラーにヴィオニエを、エルミタージュでは、ルーサンヌとマルサンヌの白ブドウを一緒に醸造する手法です。
エルミタージュでもかつては白ブドウ、黒ブドウを同じ区画で栽培(混植)していました。そうした中では混醸も自然な流れ。ですが、今では白ブドウを混醸したワインを見つけることは先ずありません。
マルサンヌかルーサンヌか:北ローヌと南ローヌの違い
コート・ロティとは異なり、エルミタージュでは、白ワインも生産されます。エルミタージュ全体で約140ヘクタールの栽培面積中、30ヘクタールほどが白ブドウに充てられています。
マルサンヌが主要品種ですが、単一品種のワインの他に、ルーサンヌもブレンドされます。アプリコットやピーチと言った有核果実やトロピカルフルーツのコクのある味わい。フローラルでフルボディの高品質のワインです。
シャプティエは、マルサンヌを支持していて、マルサンヌ100%のエルミタージュの白ワインを造っています。シャプティエだけでなく、エルミタージュでは、マルサンヌが優勢。
発酵温度は、果実感を残すため中程度。マロラクティック発酵は酸を残すために、避ける場合もあります。ボディに厚みを出すために、澱との接触(シュール・リー)や、澱を定期的に攪拌するバトナージュをシャプティエなどの生産者は行っています。発酵槽には、木桶やステンレスタンクが使われます。
マルサンヌは、オーストラリアや米国でも知られていて、特にオーストラリアのヴィクトリア州のマルサンヌは有名。タービルク社は1927年に植樹した古木からマルサンヌのワインを15℃以下の低めの発酵温度で、ローヌとは異なったスタイルのワインを造っています。
一方で、親子関係があると言われている、ルーサンヌ。マルサンヌよりアロマティックでエレガントだとも言われています。でも、かび病などへの耐性が弱く、栽培が難しく収量も低くなるとされています。
南ローヌのシャトーヌフ・デュ・パプでは、マルサンヌは使用品種として認められていません。トップ生産者の一つ、シャトー・ド・ボーカステルは、赤ワインは認定13種類のすべてのブドウ品種を使っている一方で、白ワインでは、ルーサンヌ100%の単一品種ワインを造っています。
なお、ごく少量ですが、甘口のヴァン・ド・パイユも造られています。ブドウが良く熟したヴィンテージで、収穫したブドウを、わらの上で乾燥。比較的高めの温度で発酵、1年程度の樽熟成を経て、残糖150グラム程度の甘口に仕上げます。
6. 大手生産者たちの牙城
この産地では、20社ほどの生産者がワイン造りをしていますが、シャプティエ、ポール・ジャブレ、ジャン・ルイ・シャーヴが有名です。アペラシオン全体の栽培面積の半分をこの3社で占めます。
シャプティエはビオディナミを積極的に導入。完全除梗して、新樽も5割程度と積極的に活用しています。発酵槽は開放型の木樽を使用。単一区画キュヴェの、レルミットとル・メアルでは赤ワインと白ワインの両方を、リリースしています。
ポール・ジャブレは、ボルドー・オーメドックの格付け3級シャトー・ラ・ラギューヌを所有するフレイ家に売却されました。トップ・キュヴェのラ・シャペルは、90年代以降、ジャブレ家内での不幸や生産過剰も重なり、品質が低下。フレイ家の努力で品質が向上したと言われています。
ジャン・ルイ・シャーヴは、例えば土壌が花崗岩からレス土壌へと移り変わる様に、夫々の区画は異なる個性を持っていて、それらをブレンドする事で真のエルミタージュが表現できると主張します。
カーヴ・ド・タンは潤沢な設備投資を惜しまない、評価が高い生産者組合。産地最大規模のシャプティエや、ポール・ジャブレ、ジャン・ルイ・シャーヴと並ぶ、栽培面積を有しています。
コート・ロティの大手生産者、ギガル。コート・ロティでは、単一畑の「ラ・ラ」シリーズで有名です。でも、エルミタージュの高級ライン、エクス・ヴォトでは、レ・ベサール、レ・グレフュー、レルミットなどの区画をブレンド。

by Ricochet64 – stock.adobe.com
ギガルの白ワインは、50年以上の古木から収穫したマルサンヌとルーサンヌを使います。100%新樽を使った発酵で樽熟成も30か月と贅沢。この白ワインは、もしかすると赤ワインよりも長期熟成するのではと評されるほどです。
7. 試してみたいエルミタージュの優良ヴィンテージ
せっかくエルミタージュを飲むなら、良いヴィンテージを試したいですね。
2015年は豊満でフレッシュさもあり、長期熟成が可能な素晴らしいヴィンテージ。でも白ワインは少しリッチ過ぎるとも。
2018年もリッチでパワーがある良いヴィンテージで早くから楽しめます。2019年は、バランスが良いヴィンテージ。
少し熟成が進んだものでは、2010年は収量が低く、バランスが良くて骨格がしっかりした長期熟成に向いた素晴らしいヴィンテージ。白ワインは凝縮度にも骨格にも恵まれたヴィンテージです。2009年は暑く乾燥した夏のお蔭で、パワーが有って成熟度が高いヴィンテージ。2005年は、凝縮度と熟成可能性に恵まれた、とても良いヴィンテージです。
一方、2012年、2013年や、2007年、2008年は難しい年でした。
8. エルミタージュのまとめ
北ローヌでは、コート・ロティと双璧を成すエルミタージュ。その歴史や栽培、醸造にも踏み込んで今回は勉強しました。
赤ワインだけのコート・ロティとは異なり、エルミタージュでは、白ワインも、同じアペラシオンから造られています。ヴィオニエと違い、まだ知名度が低いマルサンヌやルーサンヌからも素晴らしいワインが見つかります。
生産者もコート・ロティと違って、大手数社が大半を生産していますので、憶えておけばレストランやワイン・ショップで購入しやすいのでは無いでしょうか?アカデミー・デュ・ヴァンでも、Step-IIを始めとして産地に焦点を当てたクラスを随時開催しています。ぜひ北ローヌのワインを一緒に楽しみましょう!